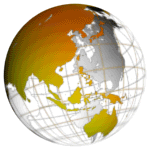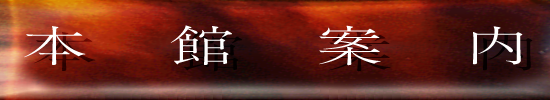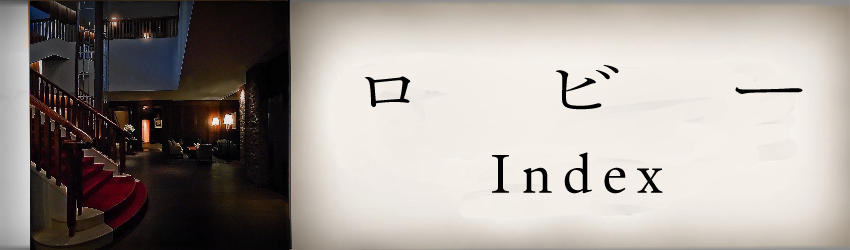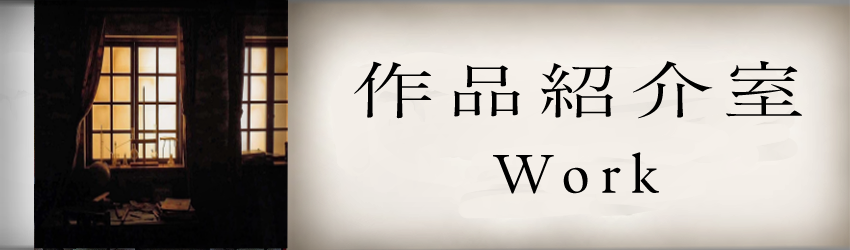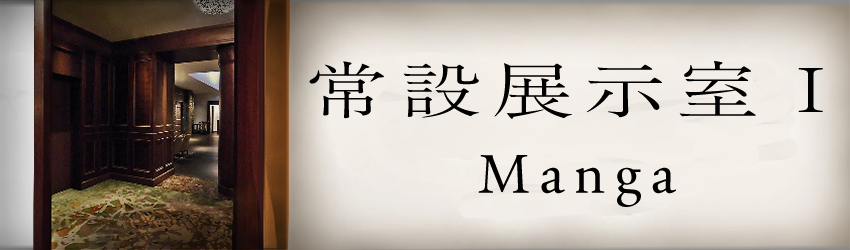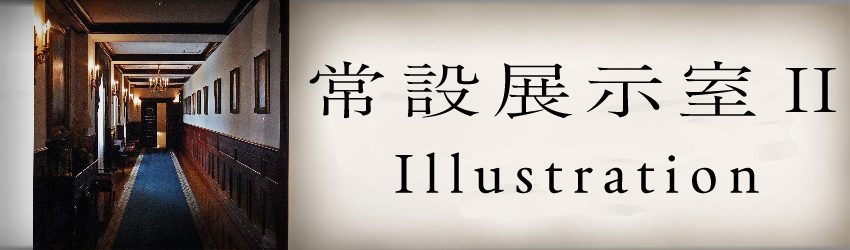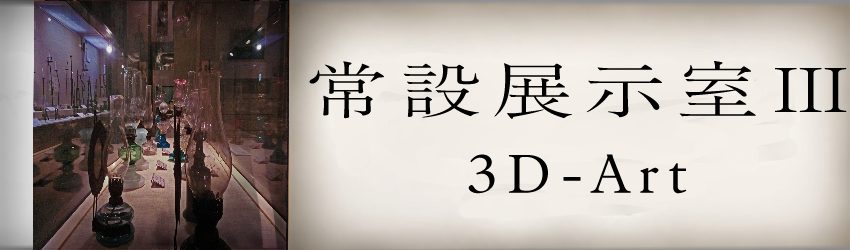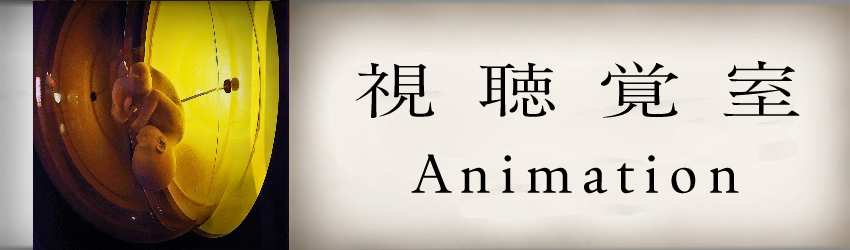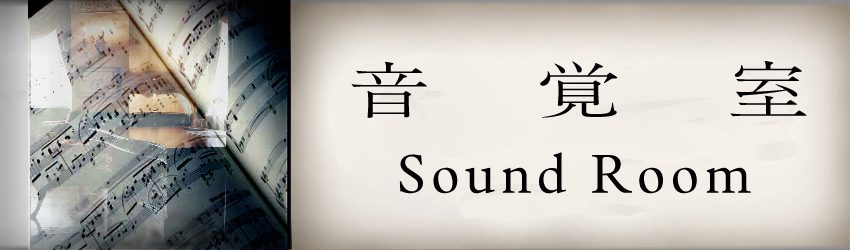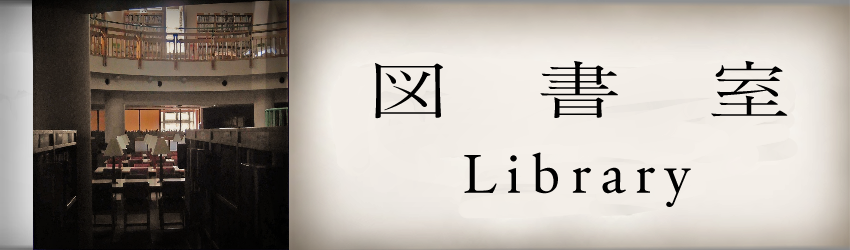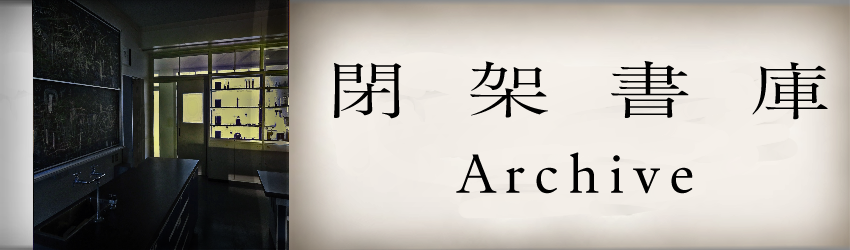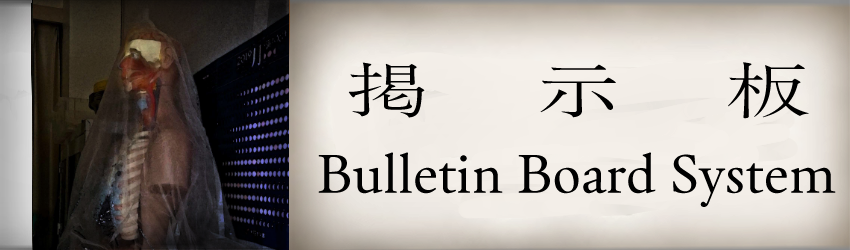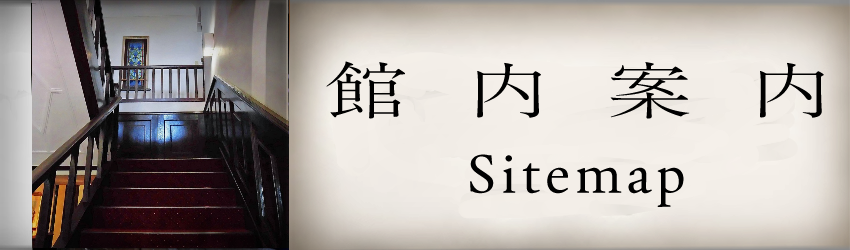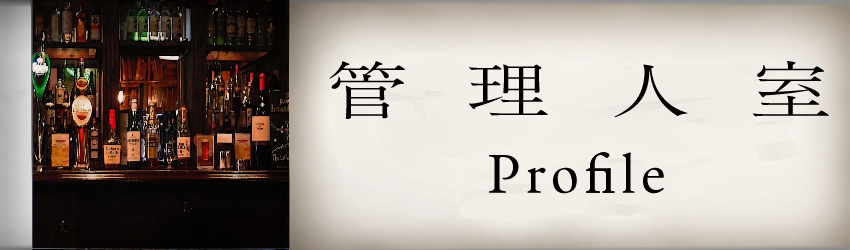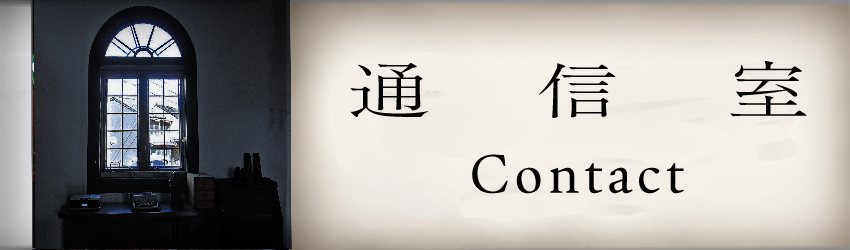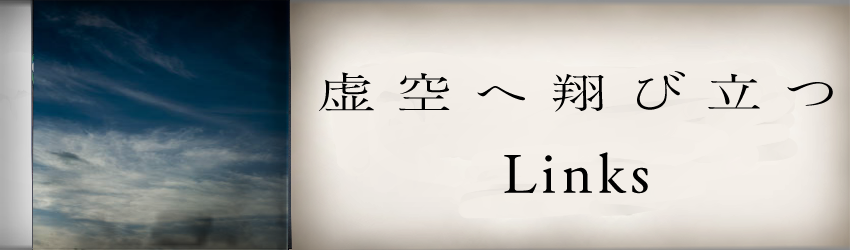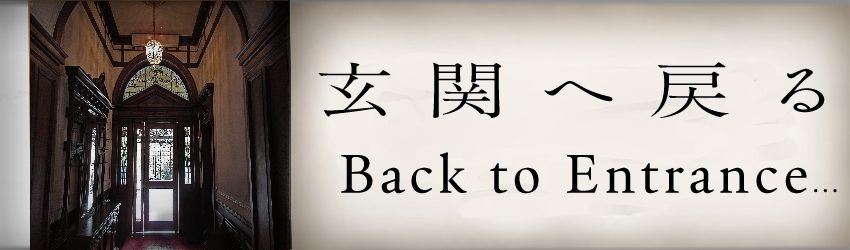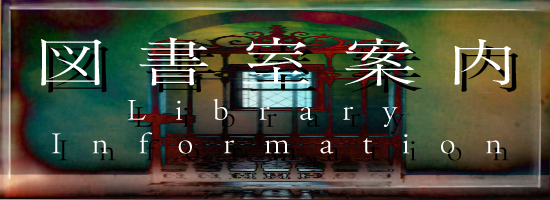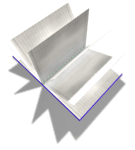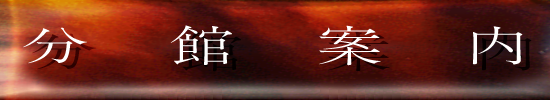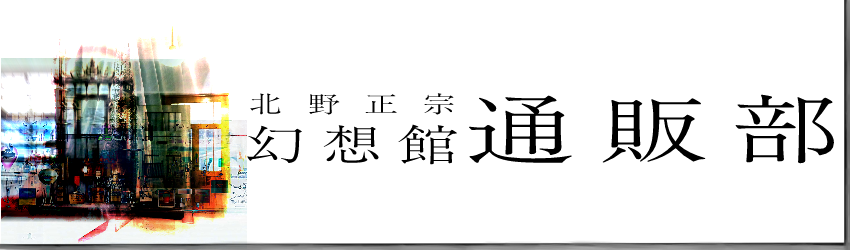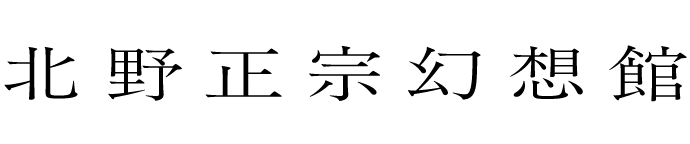私は、そもそも絶滅しそうなものやマイナーなものに惹かれてしまう。何故なら、そういったものたちが消滅して世の中が完全に一色に染まり、遠く先まで何もかも見通せるようになり、人が生きていくうえでの面白みが完全に定義されてしまう――そんな状況は、ひどく退屈に思えるからだ。
だが同時に、現在の「多様性」という言葉だけが独り歩きしている状況も、やはり同じように退屈で、息苦しい。
私は同性愛者だが、実はレインボーフラッグというものがあまり好きではない。正確に言えば、同性愛を象徴する旗そのものよりも、「多様性のシンボル」を安易に虹色で表現しようとする世の中の風潮が嫌いなのだ。SDGsの虹色、リストバンドの虹色――どれも大きな流れに飲み込まれた結果であり、そこに深い考察はほとんど存在しない。私は、シンボルなんて無理に作らず、曖昧なままにしておいてほしいと思う。
なぜなら、もし本当に「真の多様性」を求めるのであれば、単一のシンボルをそこに付与してはならないからだ。多様性とは、ひとつとして同じではない無数のシンボルが共存している状態を指す。にもかかわらず、それらを「ひとつの塊」としてまとめ上げ、上から一枚のシンボルを貼り付けてしまえば、結局は画一性に回収されてしまう。多様性がひとつの旗に集約された瞬間、それは「多様性」ではなくなってしまうのである。
シンボルには便利さがある。ひと目で意味を理解した気になれる。しかし同時に、それは深く考えることを放棄させる危険性を孕んでいる。現在の社会は、この「便利さ」に甘え、表面的な多様性を掲げながら、その内実を真剣に議論しようとしない。多数派にとって、多様性は生きる上で必須ではなく、むしろ自分にとって大した恩恵もないどころか、税金を割かれる「厄介ごと」にすぎない。だからこそ、なるべく早く「結論」を出して片付けようとする。
その結果、虹色は安易に「多様性の象徴」に据えられ、問題は「表面的に」処理されてしまった。だが、多様性というのは決して終わることのない課題である。一度向き合ったなら、永遠に付き合っていかねばならないものだ。数年や数十年で片付くはずがない。その覚悟を持たずに安易にシンボル化してしまったことが、むしろ多くの人々を傷つけてきた。もともとは善意から始まった運動であったとしても、現実には「侮辱」に近い結果を生んでしまっている。
正直に言えば、かつての世界のほうが、今のように「多様性推進」を露骨に掲げる前の世界ほうが、まだ健全だったように思える。マイノリティー人々の多くは彼ら彼女らなりに独自のコミュニティを築き、その中で力強く生きていた。世界が手を差し伸べなくとも、自力でみずからの居場所を作り出し、その中で息をしていた。今となっては、安易にシンボル化されてしまった「多様性」がそれを壊してしまったようにしか思えない。
私の考えは偏っているだろう。だから、話半分に聞いてもらえればいい。ただし、こうした思考に至ったのは、私自身が「安易な多様性の推進」によって傷つけられた経験を持つからだ。そして、同じような人間が私ひとりではないことも、どうか忘れないでほしい。
これから先、世の中の「多様性の推進」がどう変化していくか、私には正確な予想はできない。けれど、いずれにせよ、いくらそれに抵抗したとしても最終的には受け入れるしかないのだろう。無力さを噛みしめながらも、それが人間という存在の限界なのかもしれないと思う今日此の頃である。