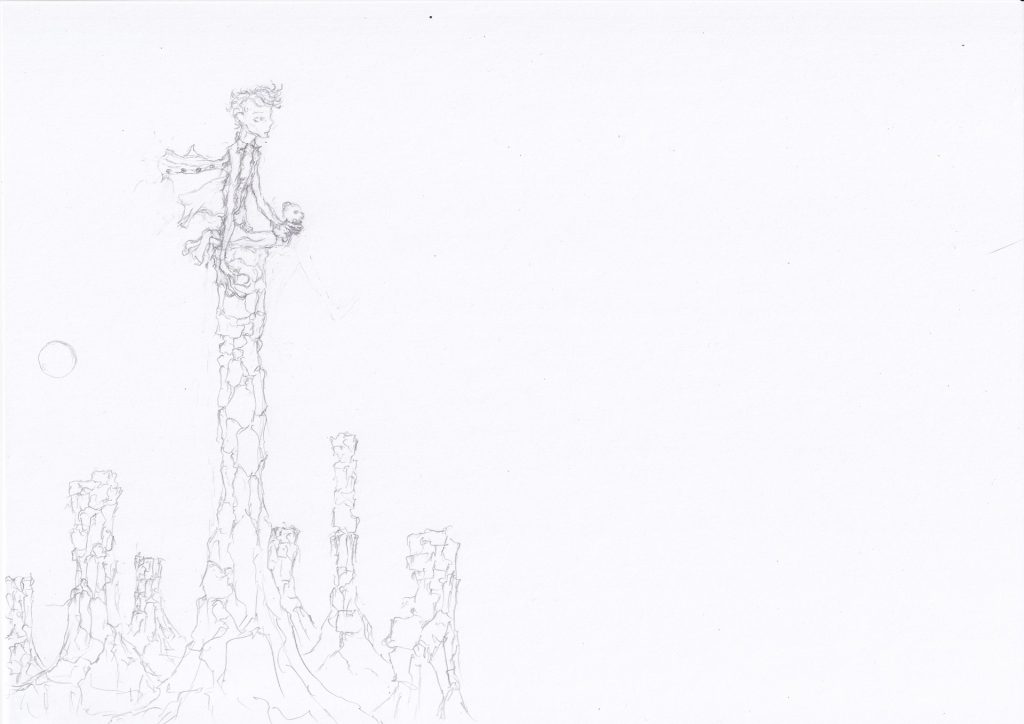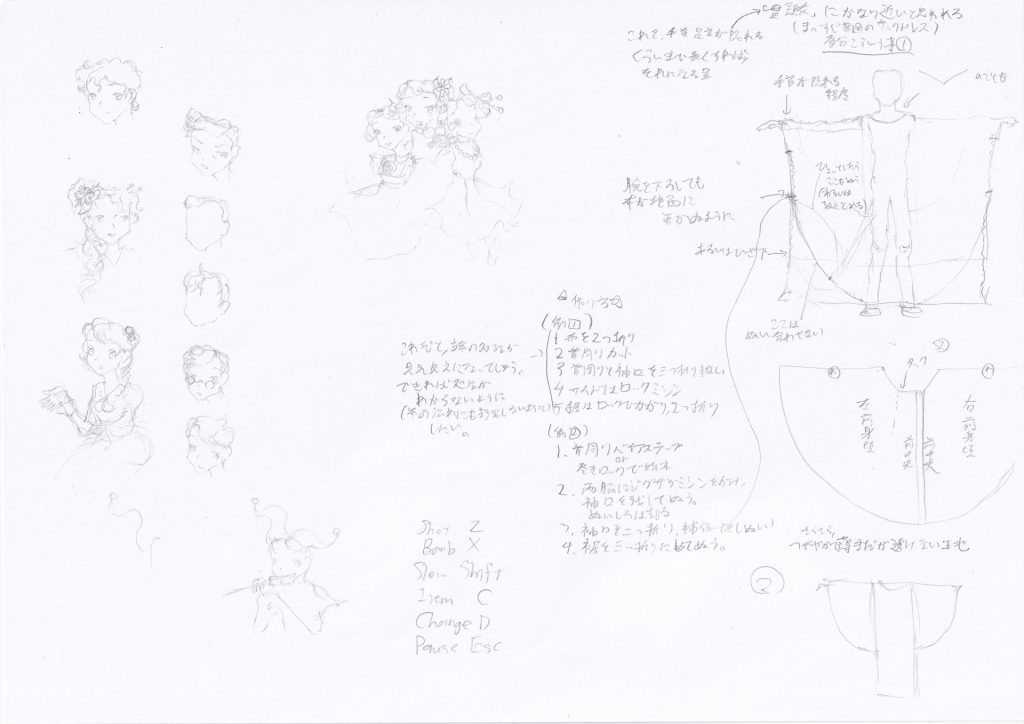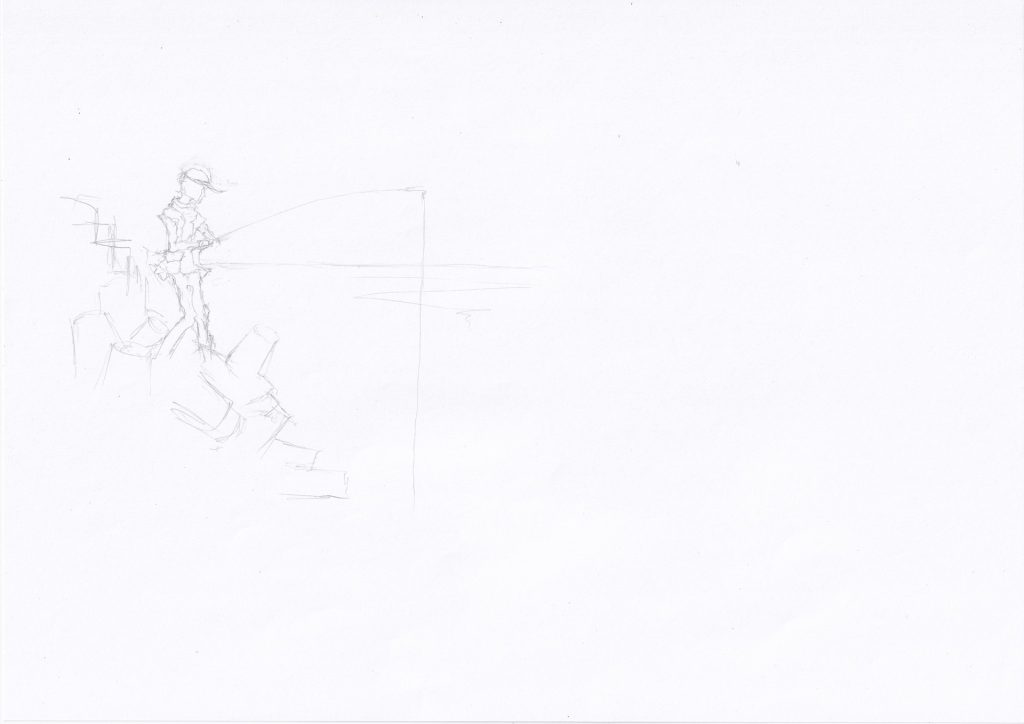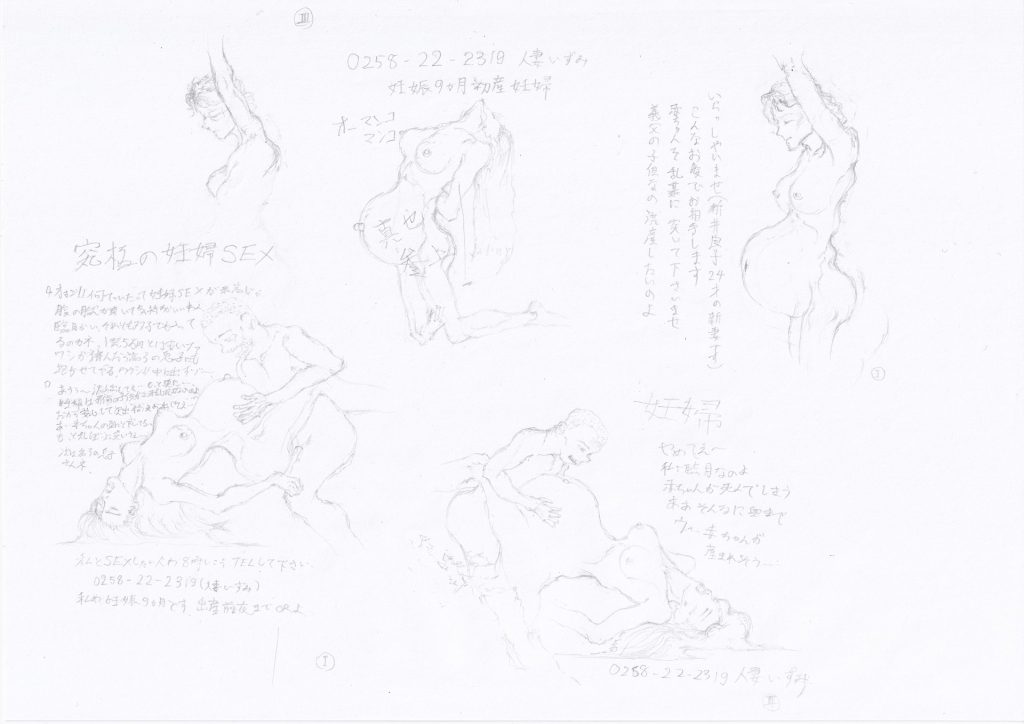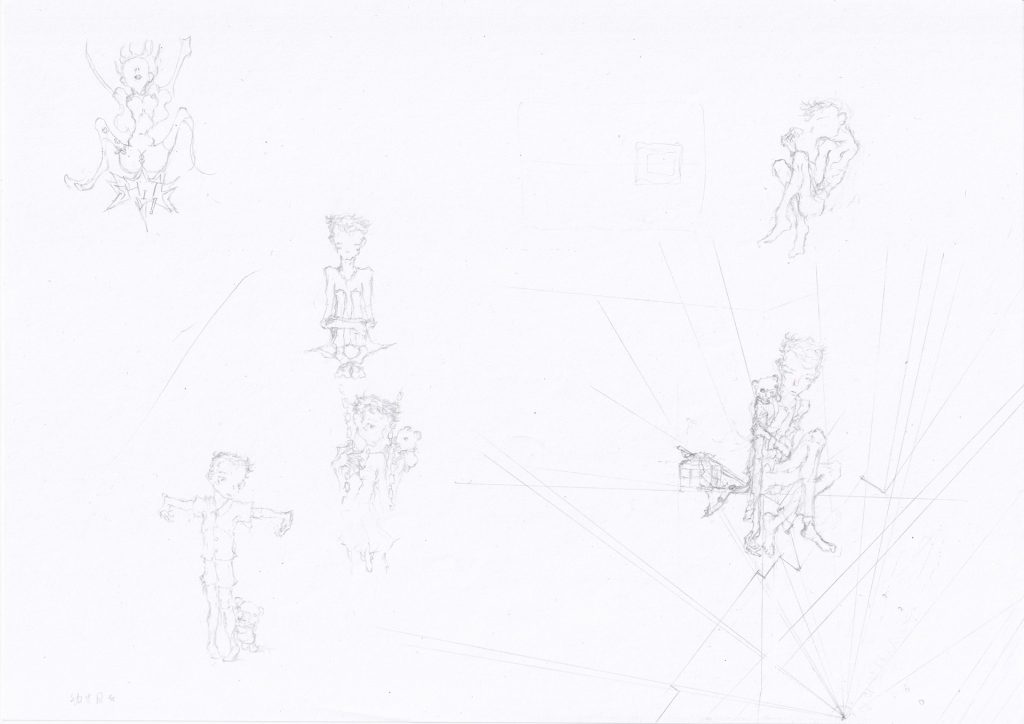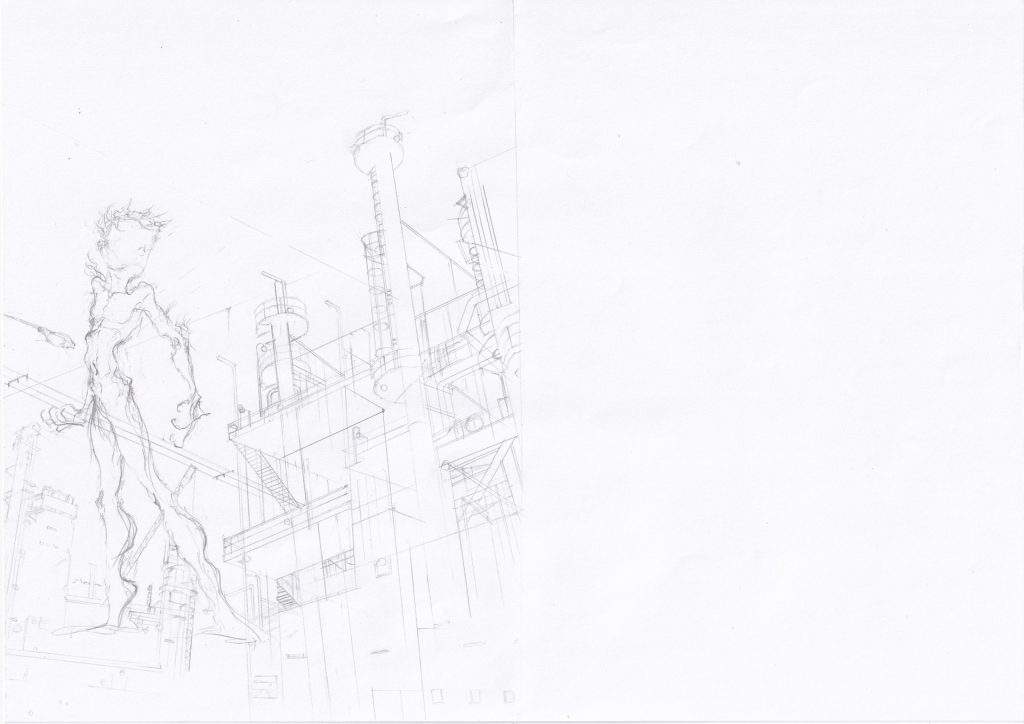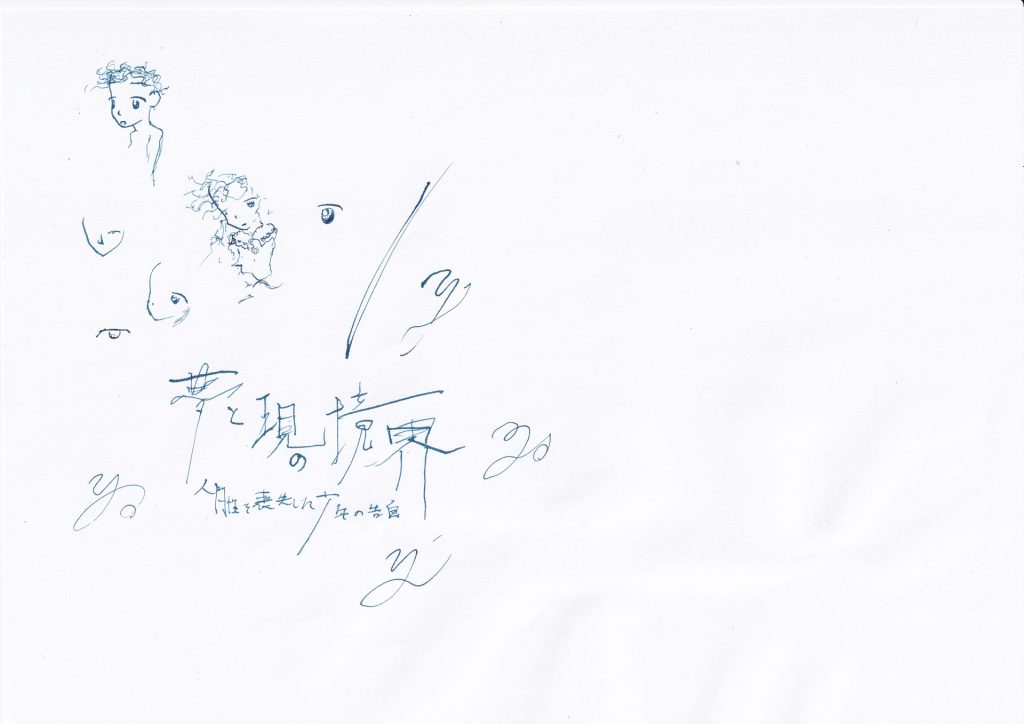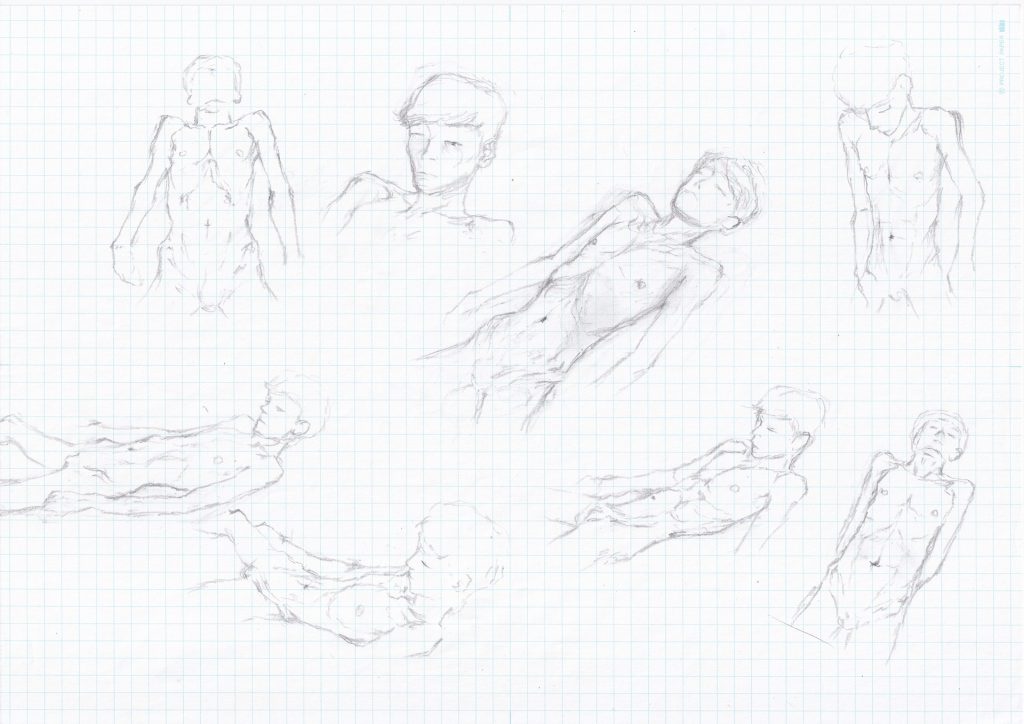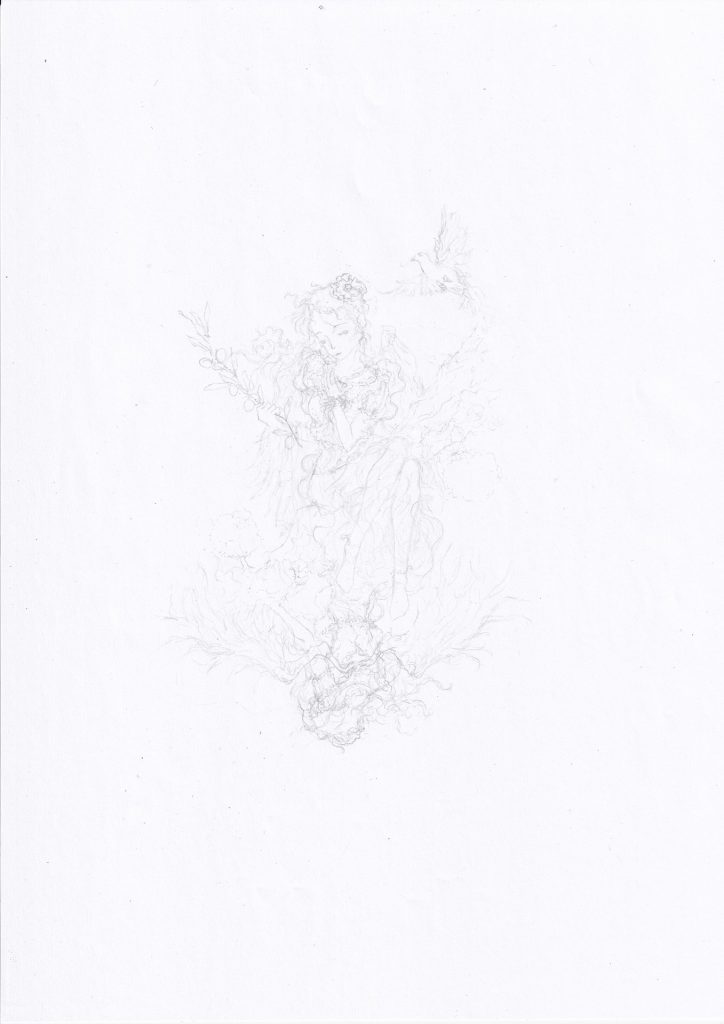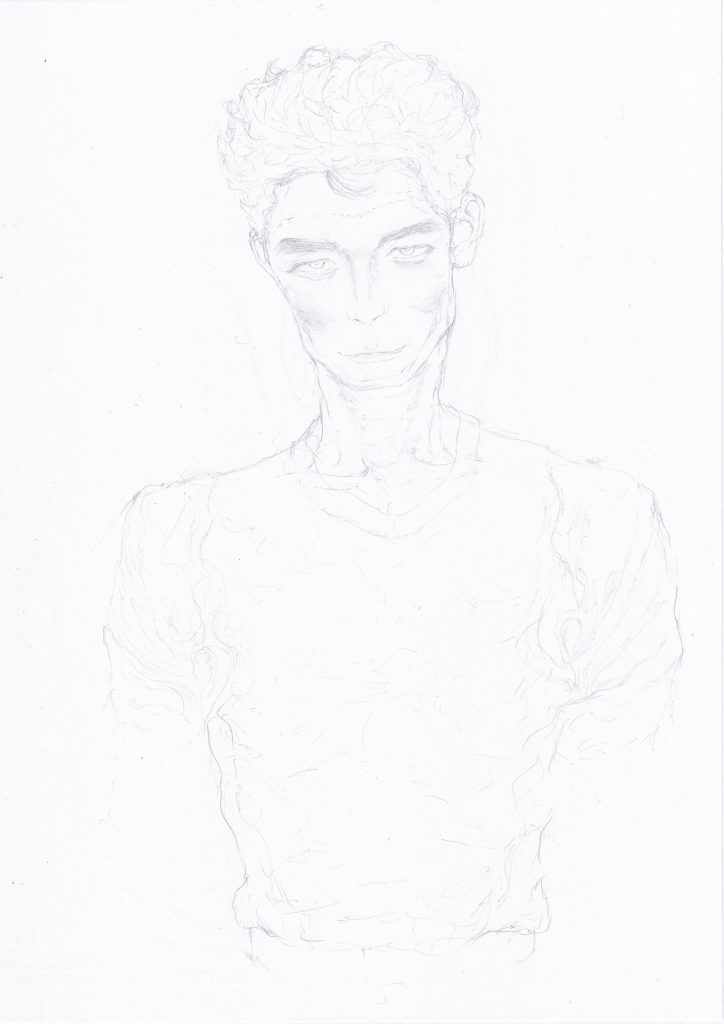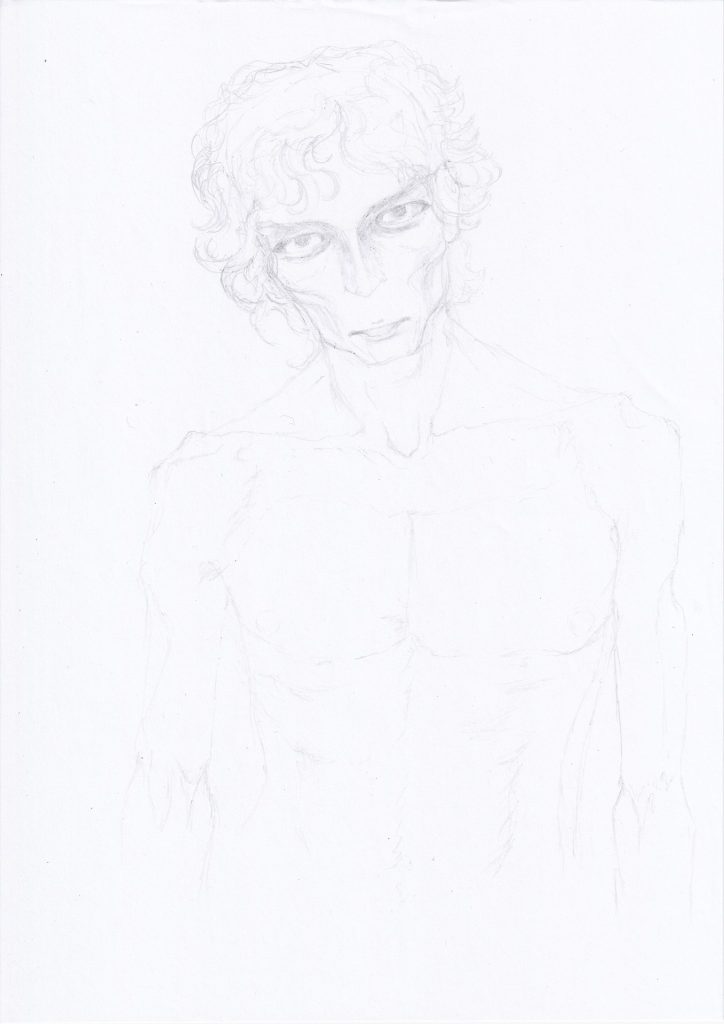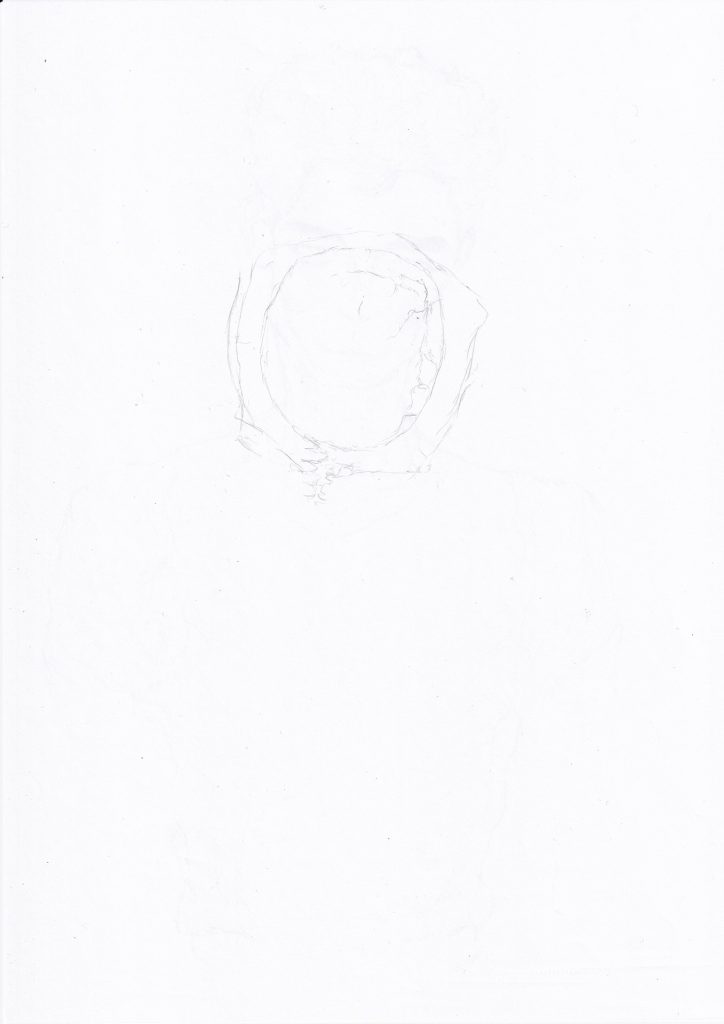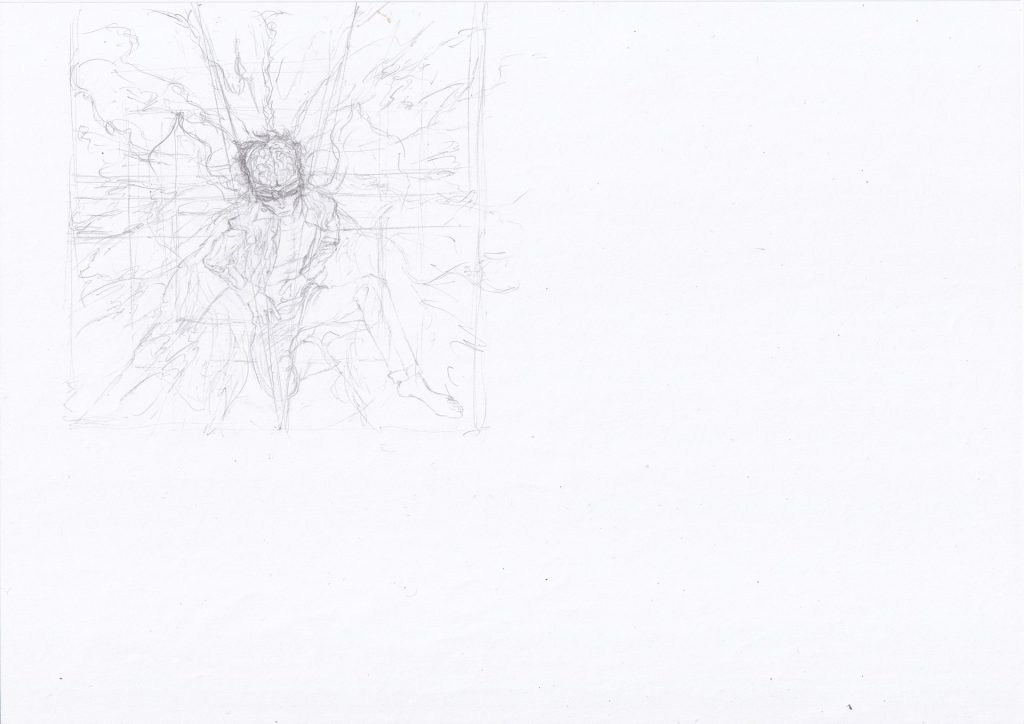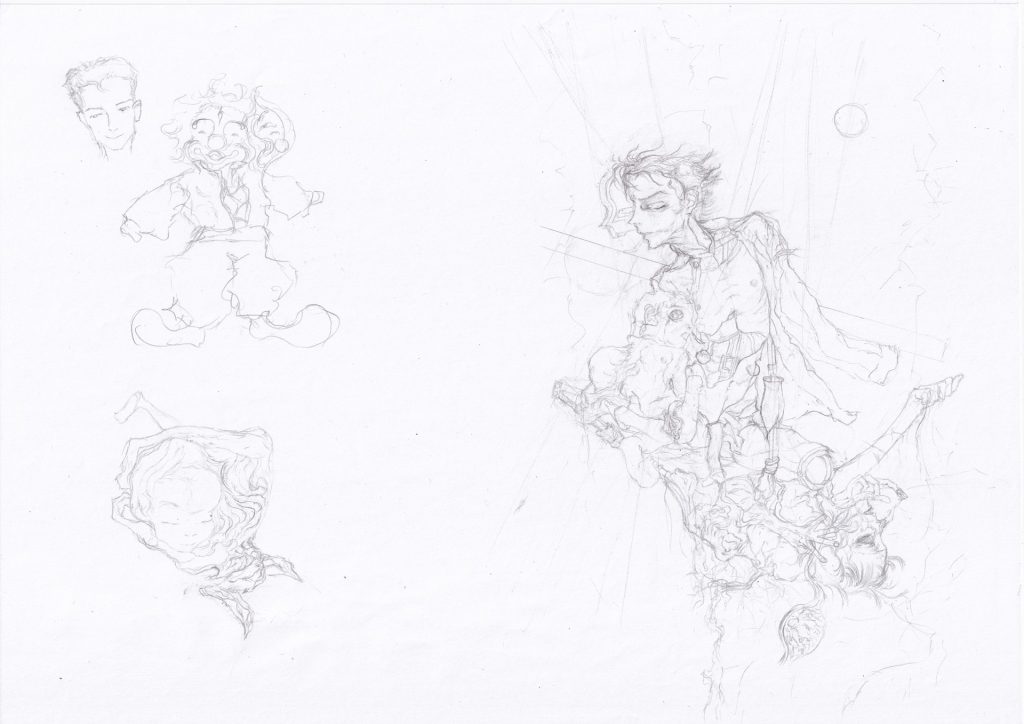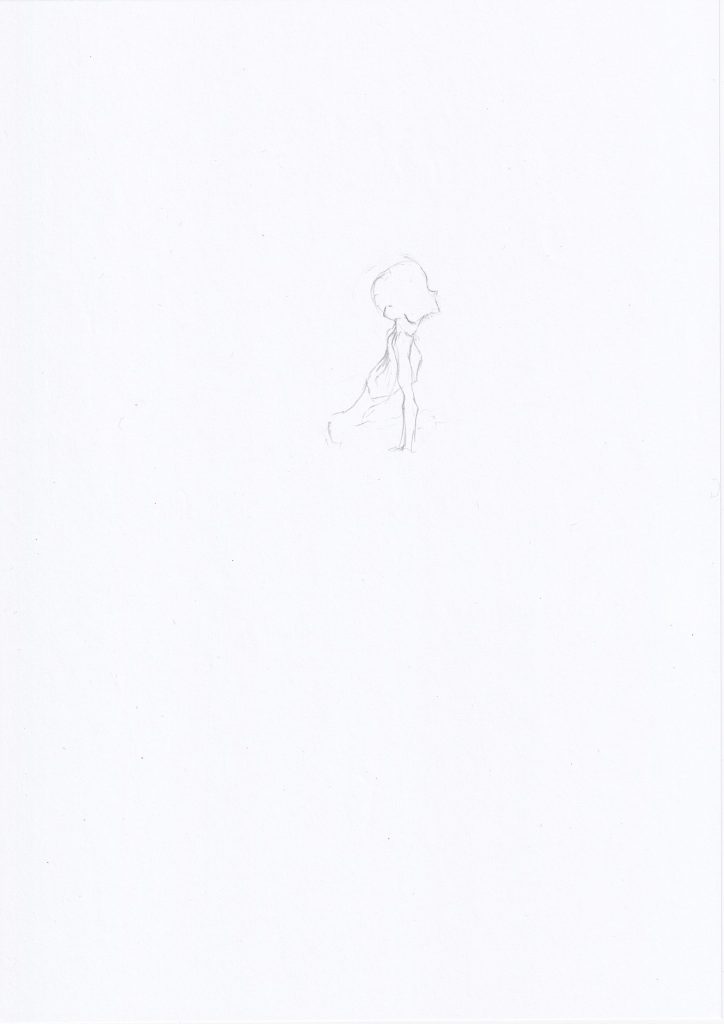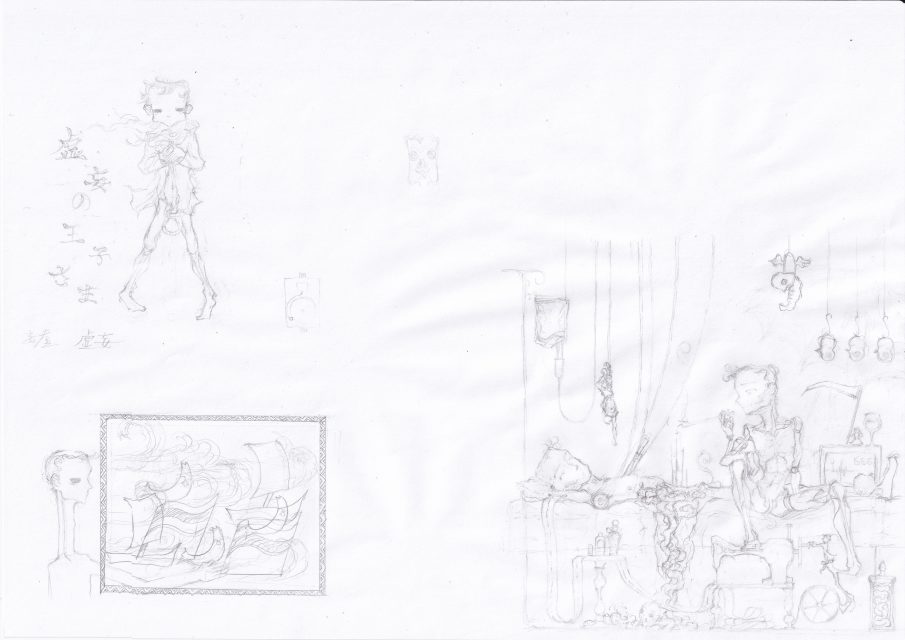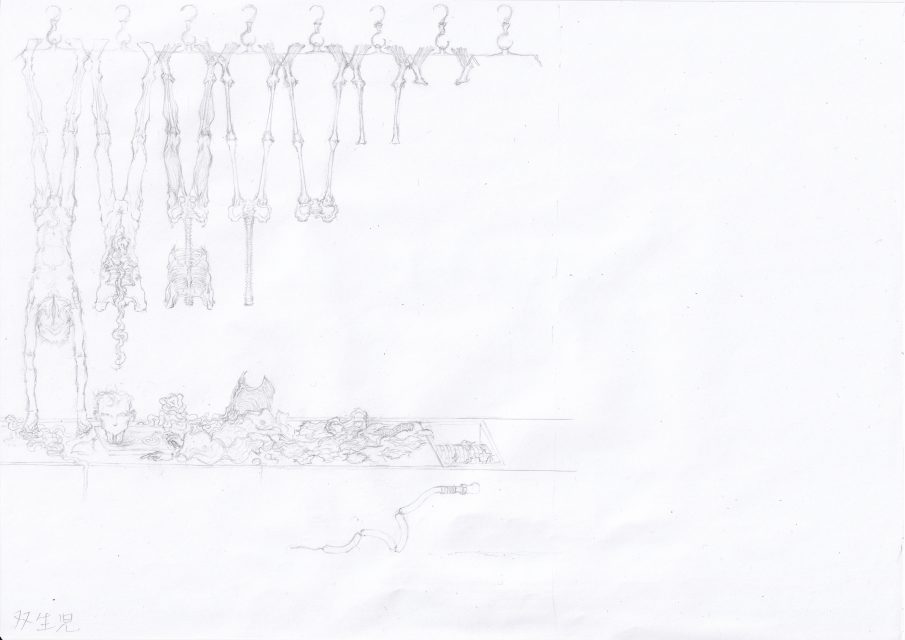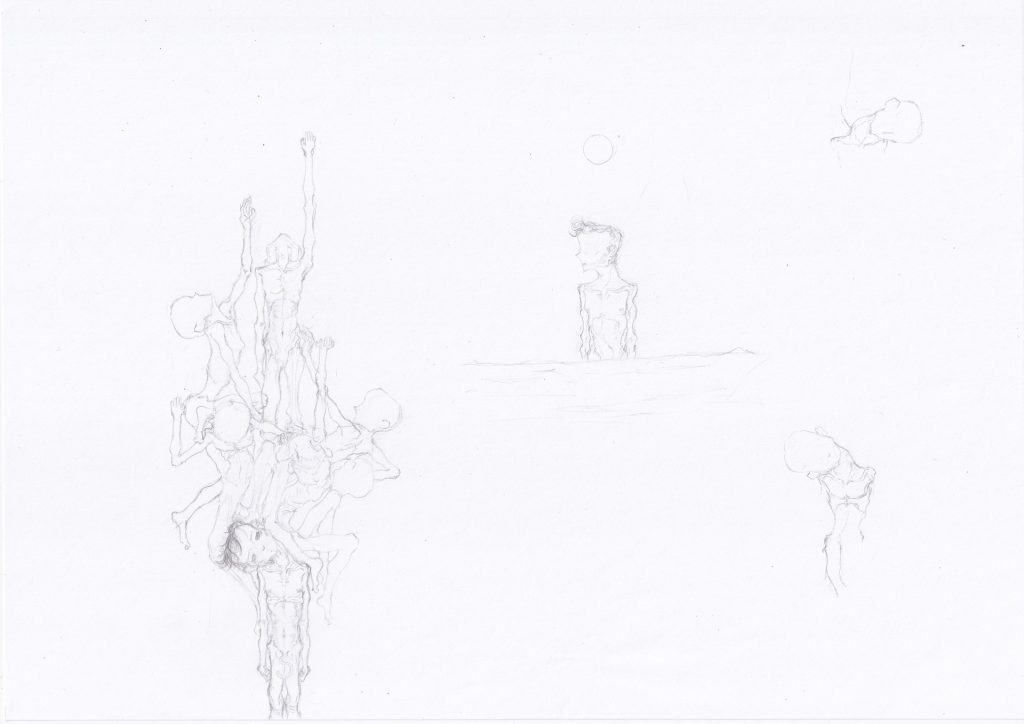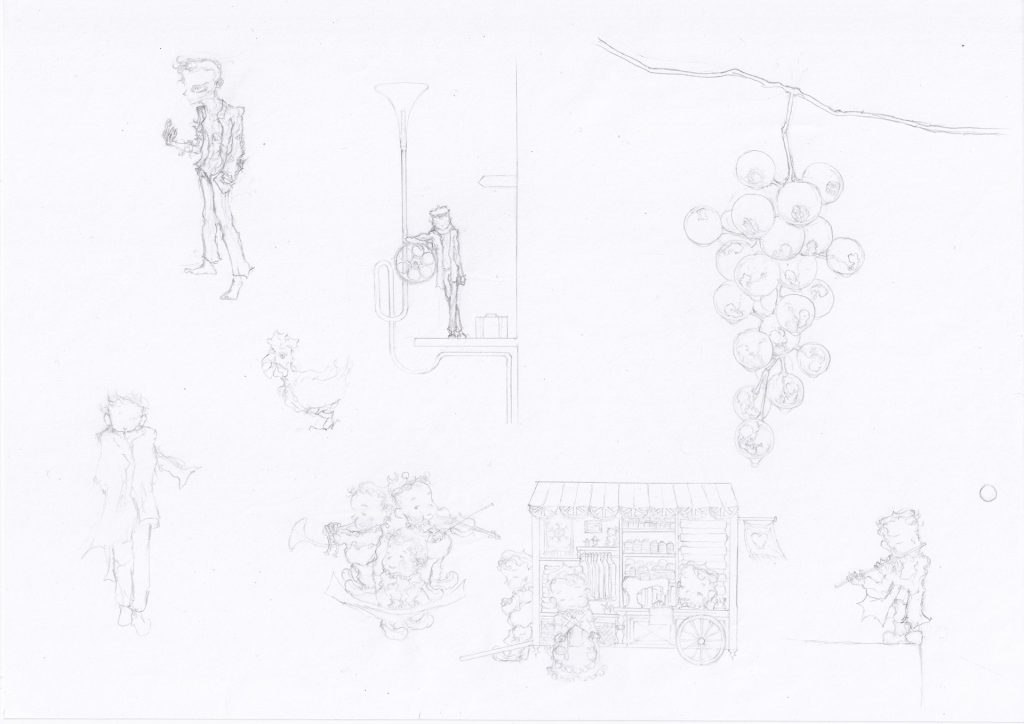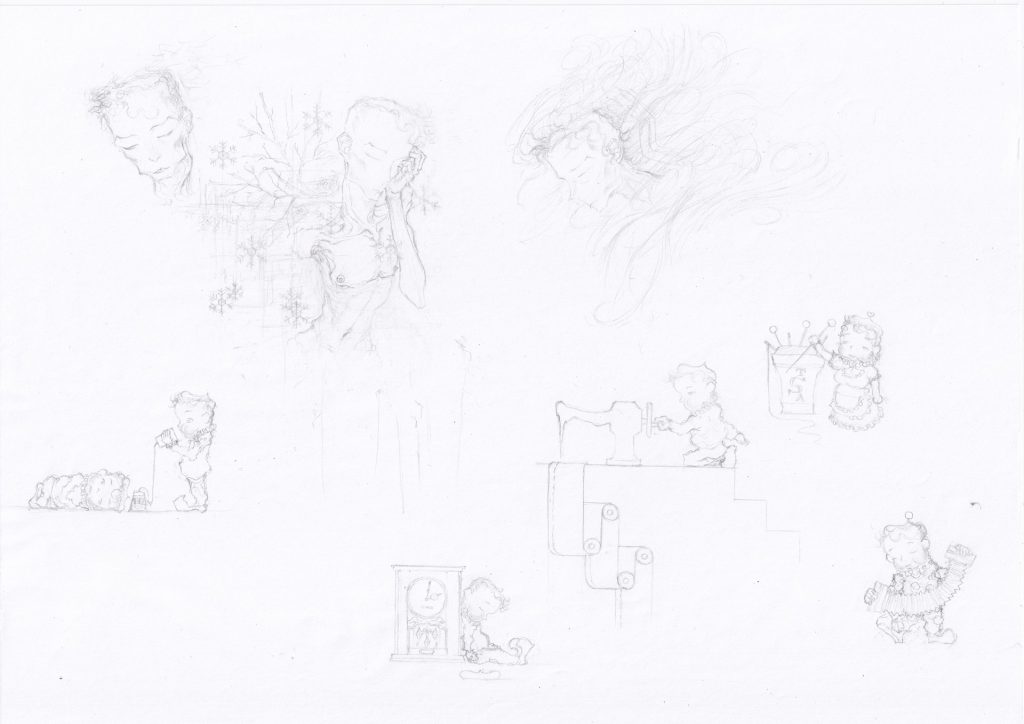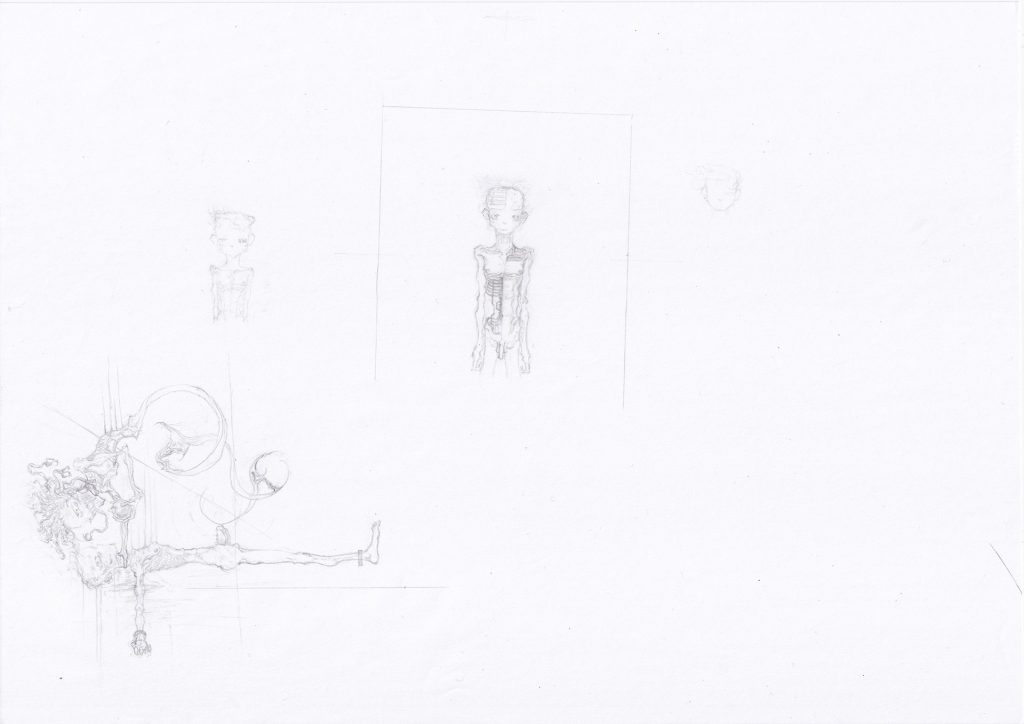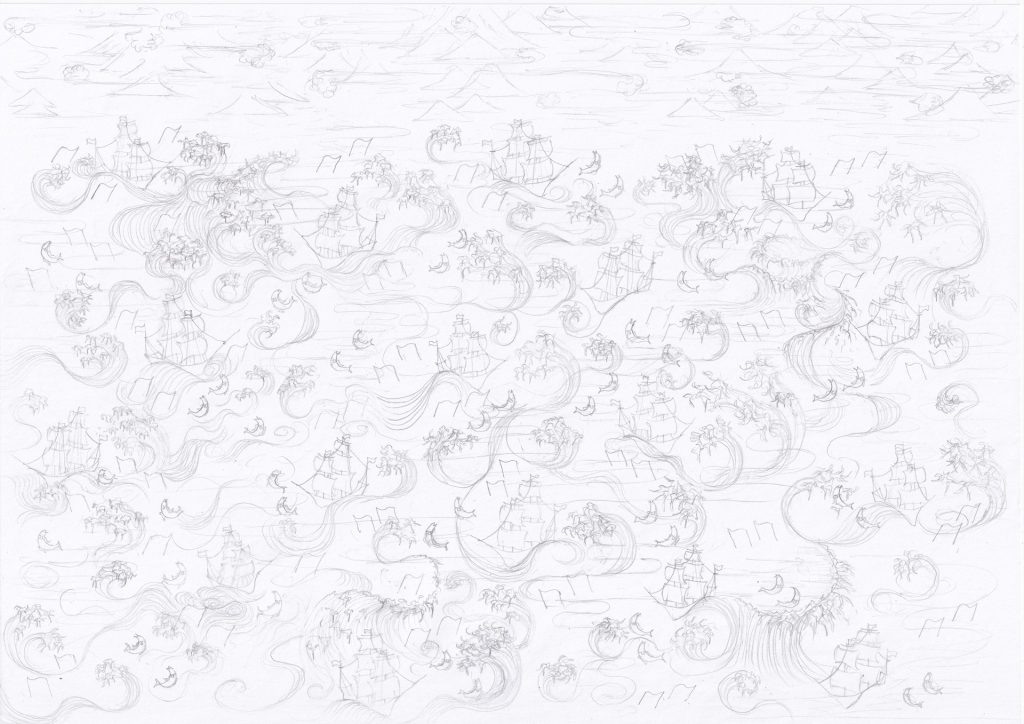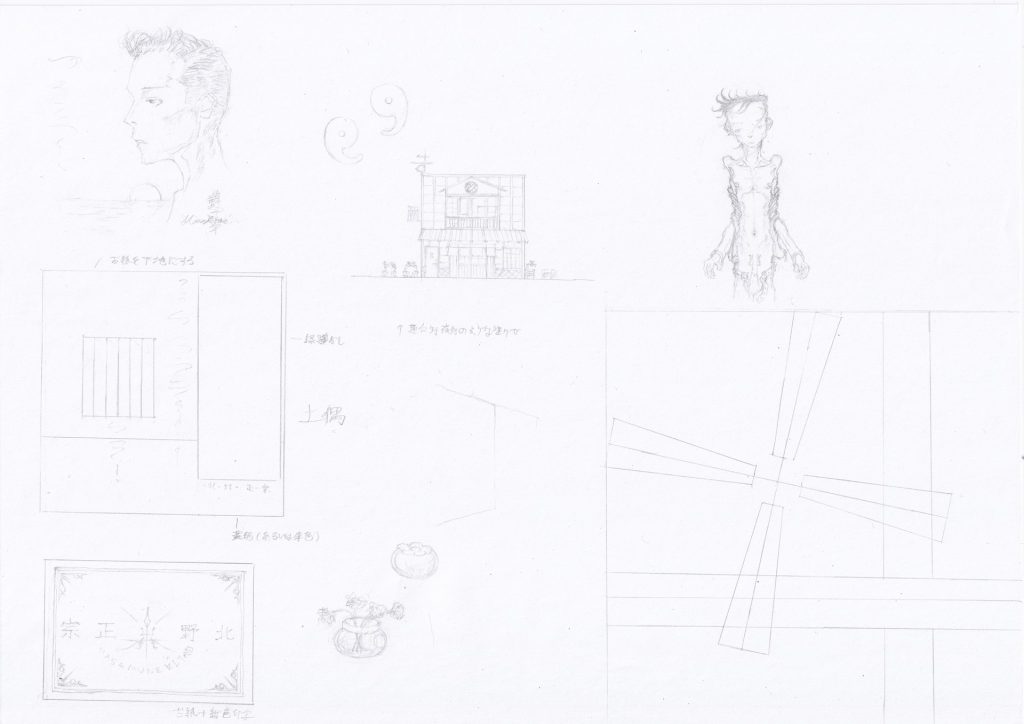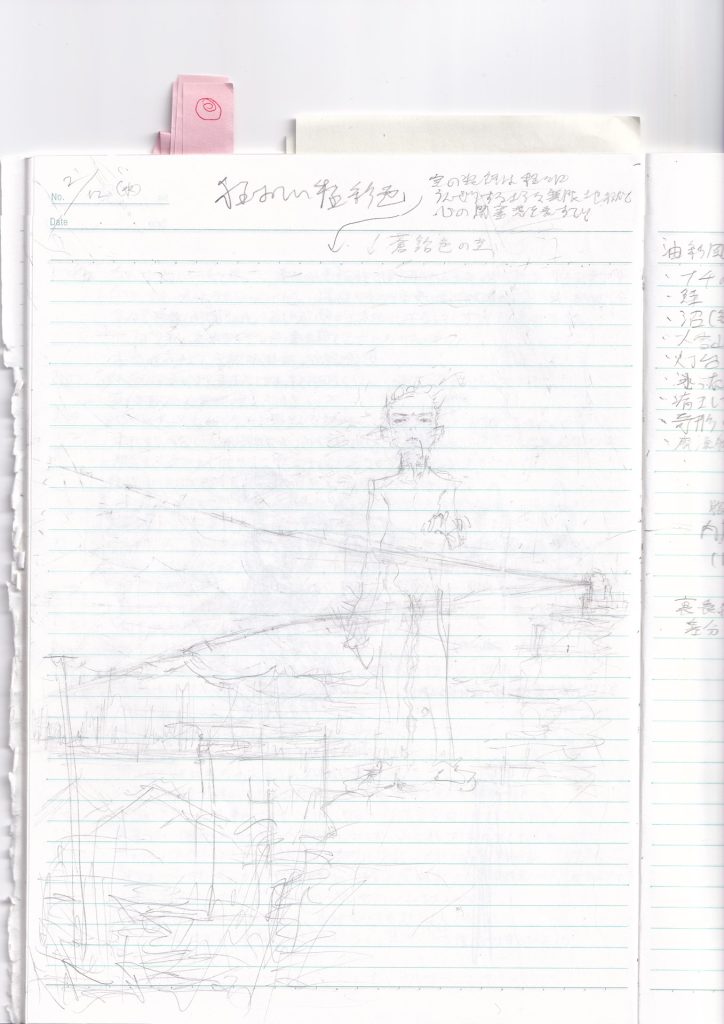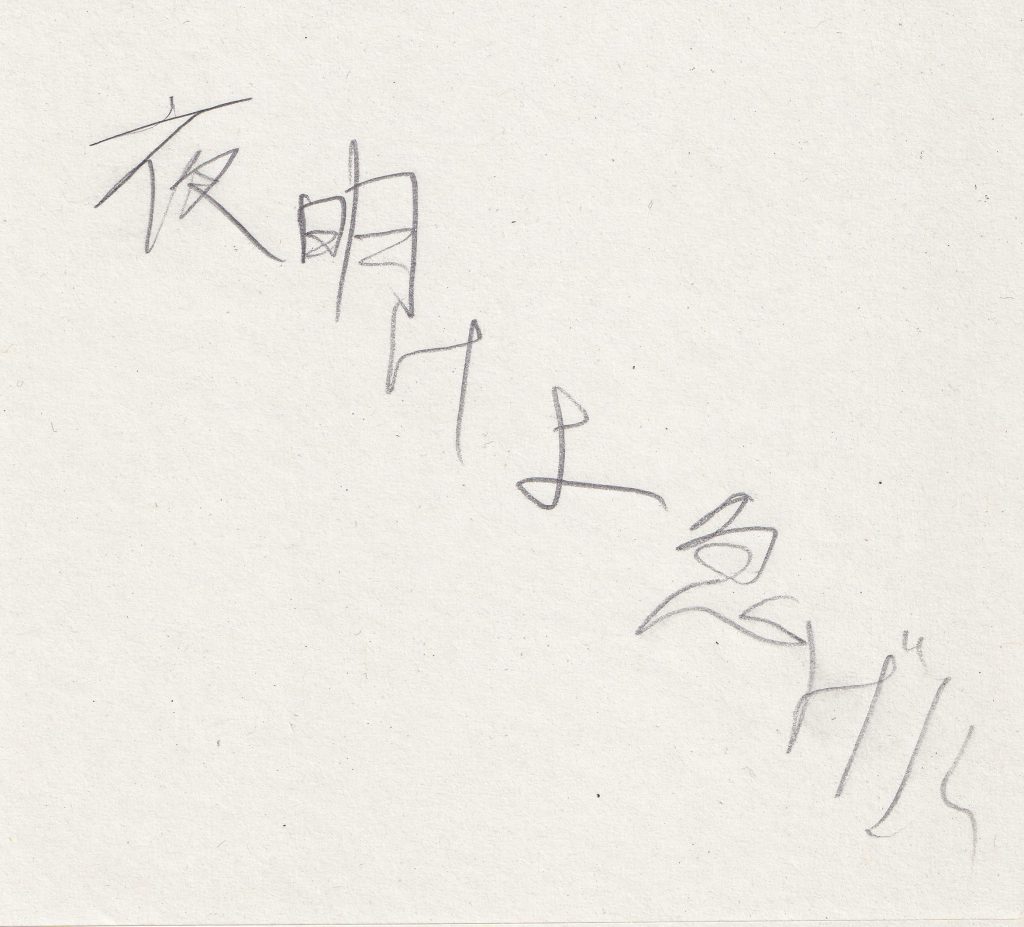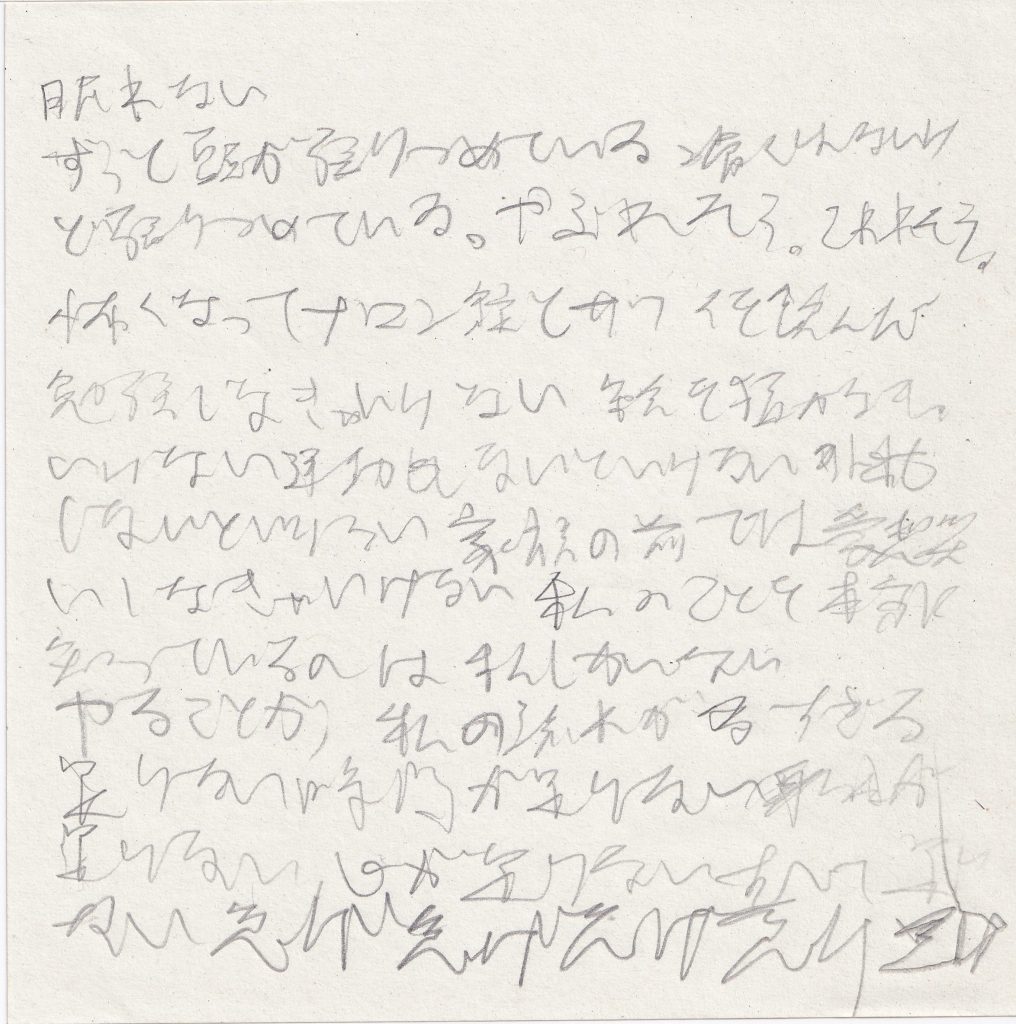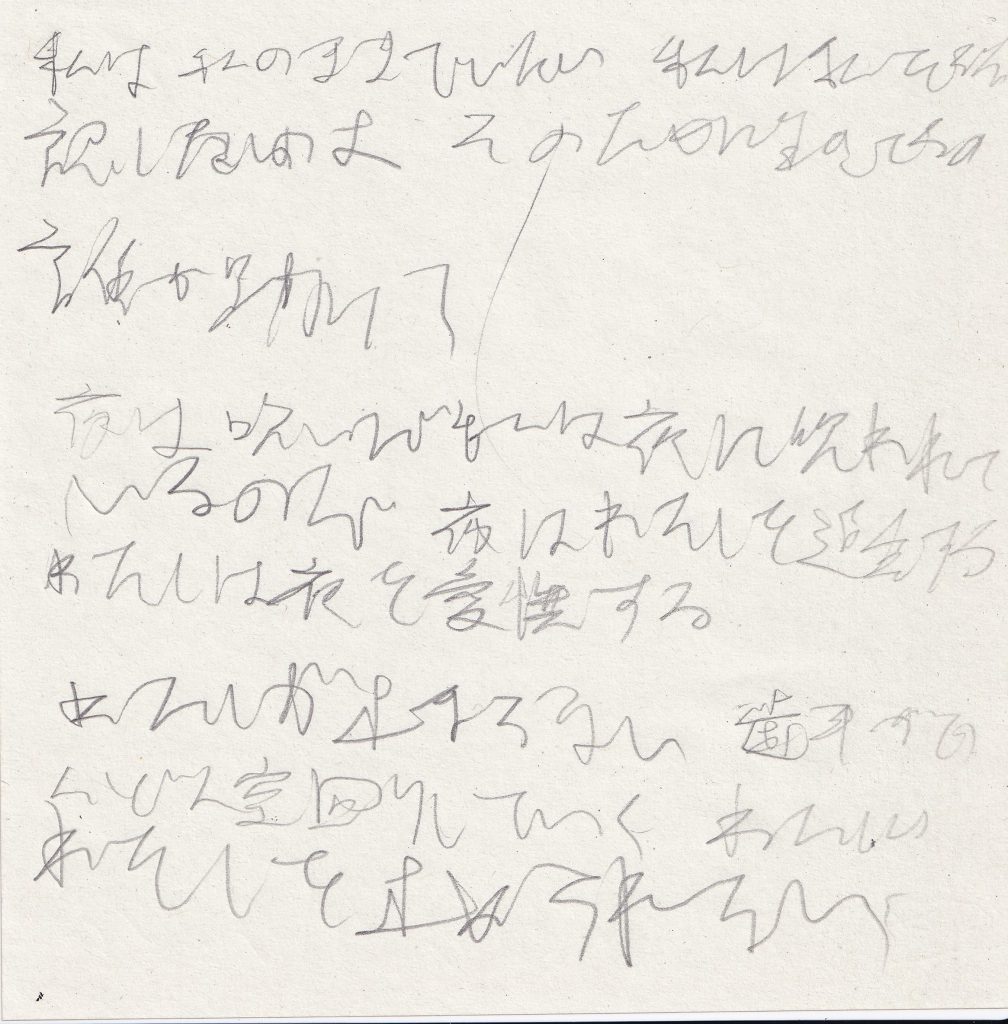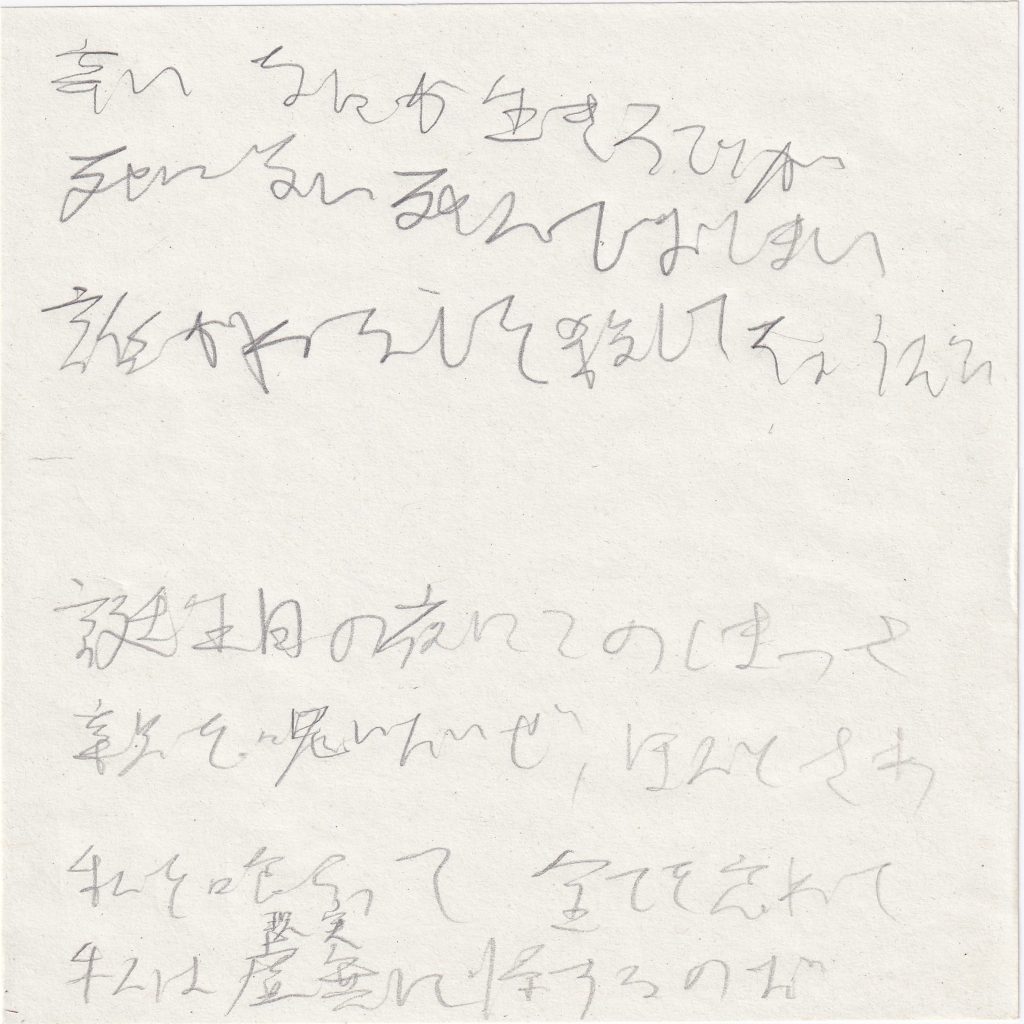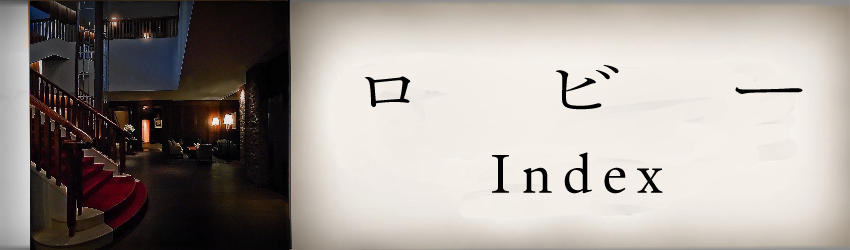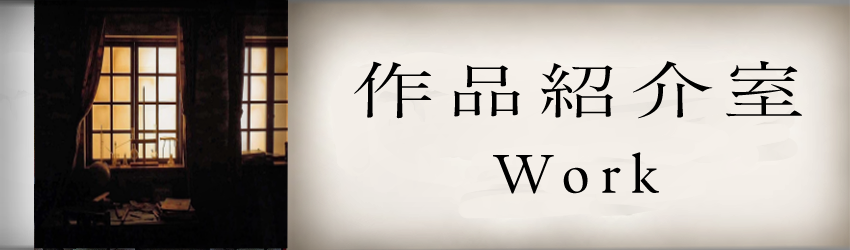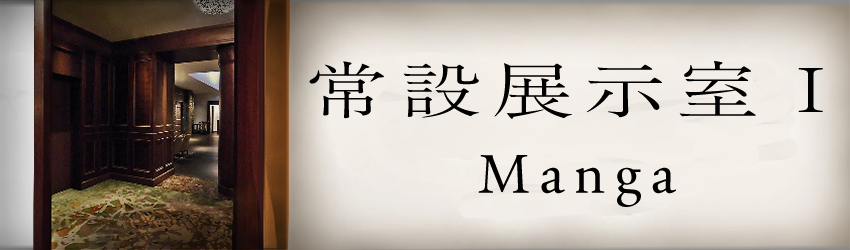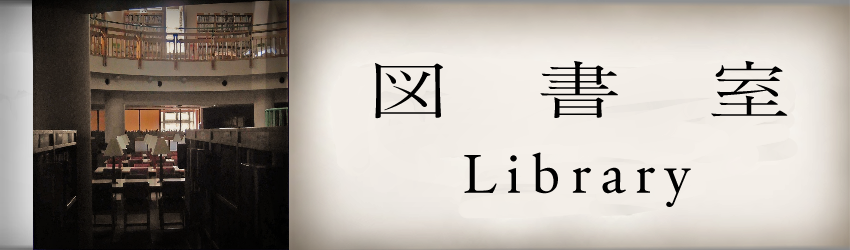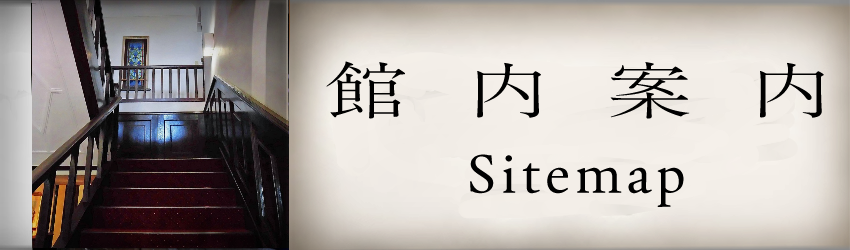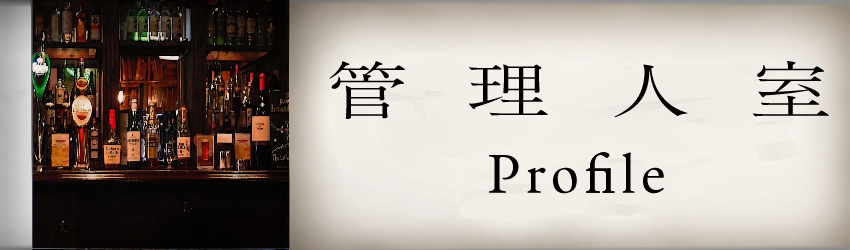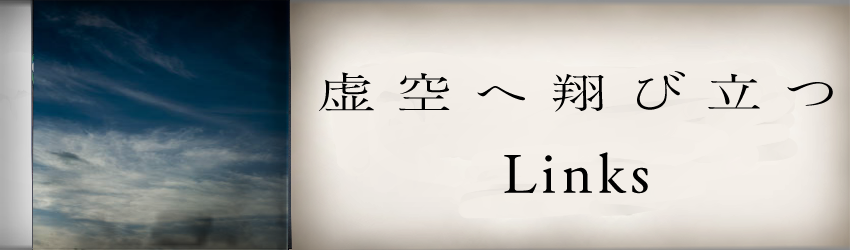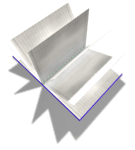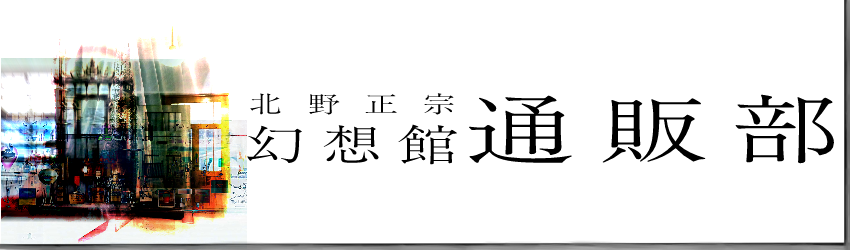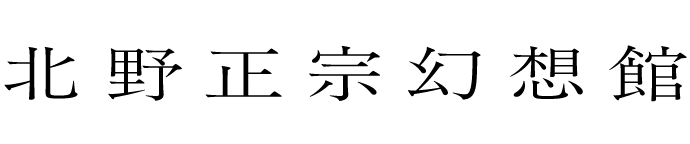夢の中の「俺」は、現実の「私」とは少し違っていた。
頼りなく、臆病で、女々しい――それが現実の私だった。
夢の中で、俺は戦争のただ中にいた。
だがそこには、戦争の実感がなかった。
戦場は無音だった。
『これは、人類最後の戦争だ』
誰に言われたわけでもない。最初から知っていた。
空には未来的な乗り物が音もなく飛び交い、地には無数の兵士たちが、機械のように歩いていた。
どんなに巨大な兵器も、輝かしい技術も、ただの飾りだった。
人々は二つの陣営に分かれ、俺はその一方に属していた。
俺一人を除いて。
俺だけが、この世界に違和感を覚えていた。
そんな俺にとって、唯一の希望があった。
夢の中でも彼とは一度も会ったことがなかった。
『僕は死にたいわけじゃない。ただ、君と一緒に、生きてみたいんだ。』
それだけのやり取りだったのに、不思議と分かっていた。
彼の存在を思うだけで、無感情な世界に、たったひとつの感情が芽生えた。
――希望だ。
彼に会いたい。
そしてある日、戦争は終わった。
俺たちの側が勝ったのだという。
雪が降っていた。
雪山の中のロッジに、俺はたどり着いた。
しかし、ただ一人だけが、微笑んでいた。
彼だった。
俺も、自然と微笑み返した。
ようやく――会えた。
彼は、ゆっくりと俺に向かって歩き出した。
その瞬間だった。
彼は崩れ落ちた。
何も言えなかった。
振り返ると、ロッジの入り口に、一人の敵兵が立っていた。
俺は、反射的に両手を上げた。
撃たれた彼のもとに、駆け寄れなかった。
なぜか?
簡単だ。俺は、自分を守った。
その事実が、これまで経験してきたどんな出来事よりも俺の心を貫いた。
これまで、俺は「自分は周囲と違う」と思っていた。
だが――
彼を見殺しにした俺と、心を持たない群衆に、どれほどの違いがある?
むしろ、心なき群衆の方が誠実ではないか。
本来なら、俺は泣き叫び、彼に駆け寄って、一緒に撃たれて死ぬべきだった。
本当は、好きだったのに。
それすらできなかった俺は、ただの卑怯者だ。
醜い自我だけを抱えたまま――
俺は、本当の意味で、たった一人になった。
――気づけば、目を覚ましていた。
それらすべてが、やけに現実的で、やけに空虚だった。
息をするのが苦しかった。