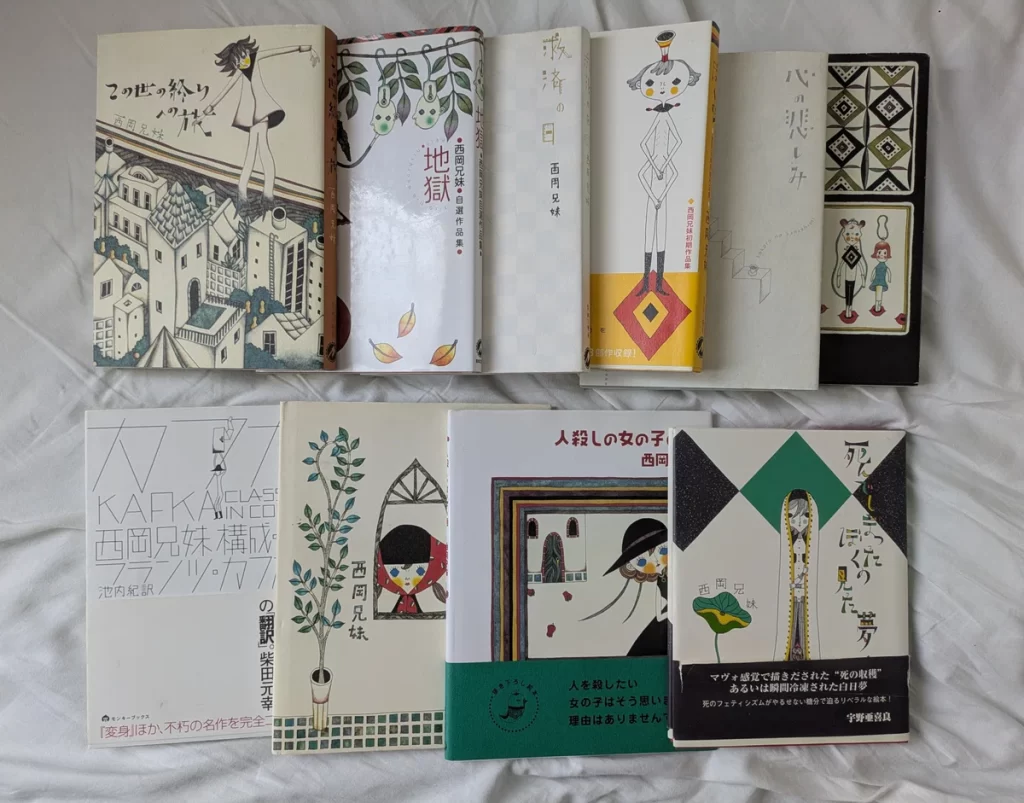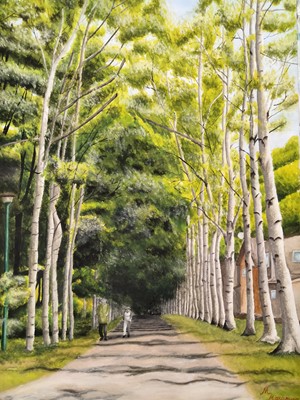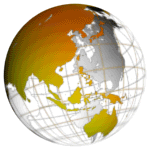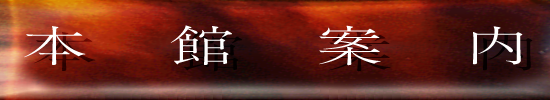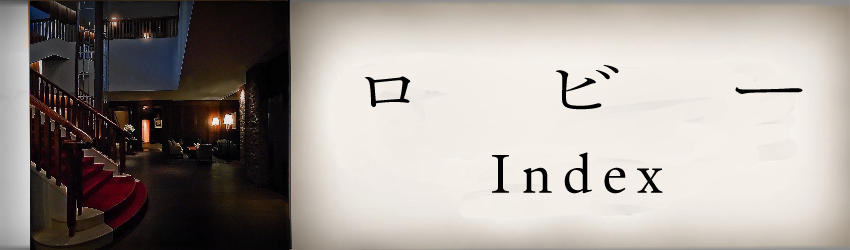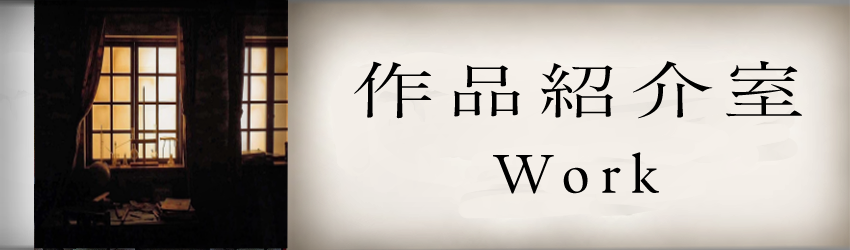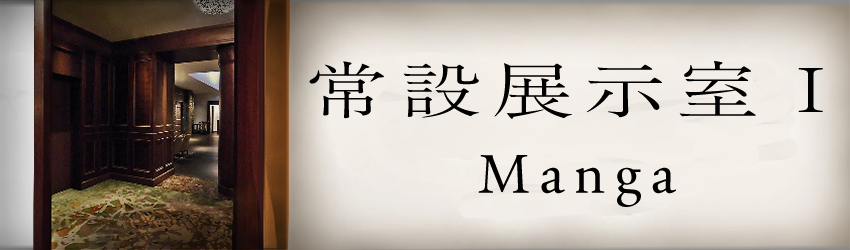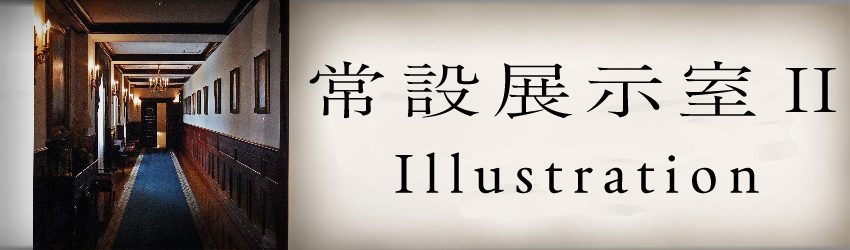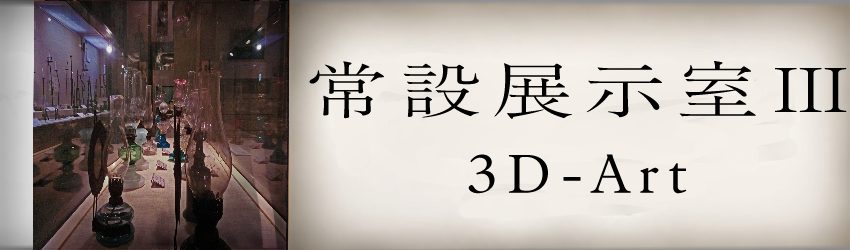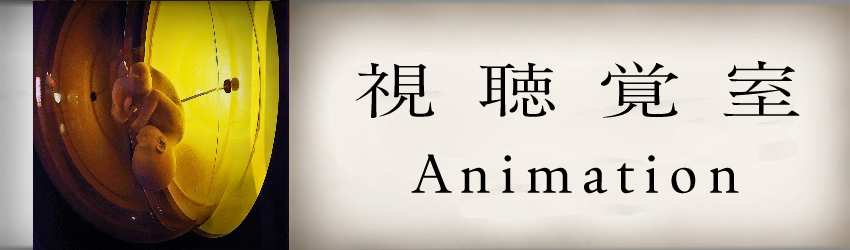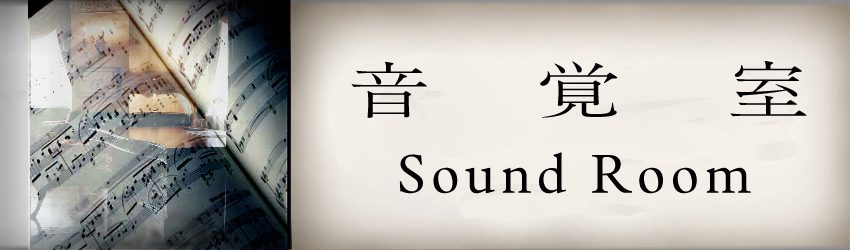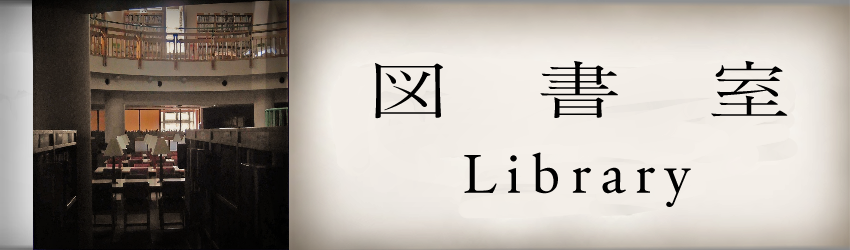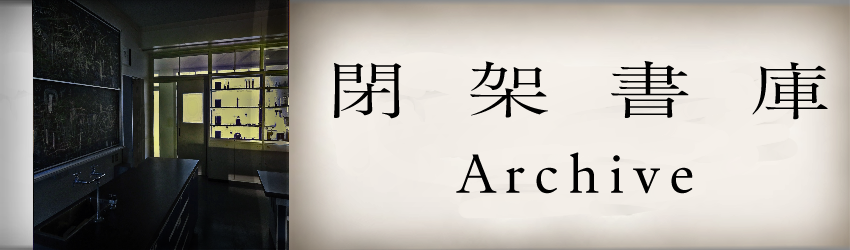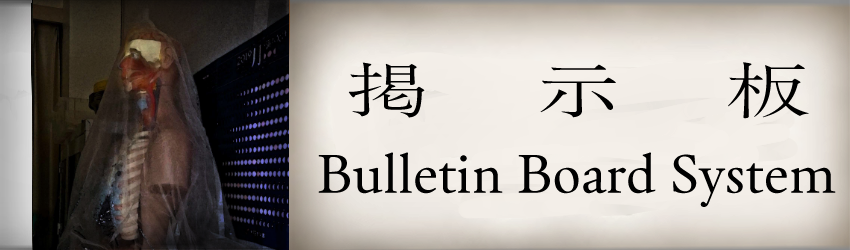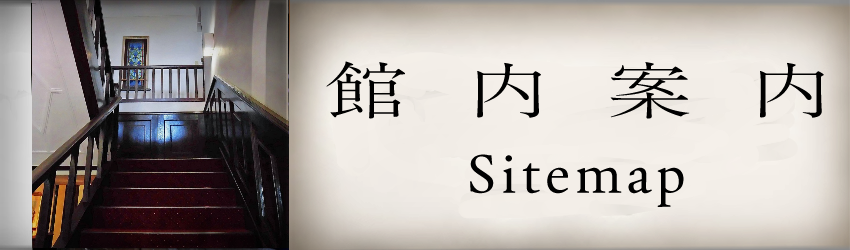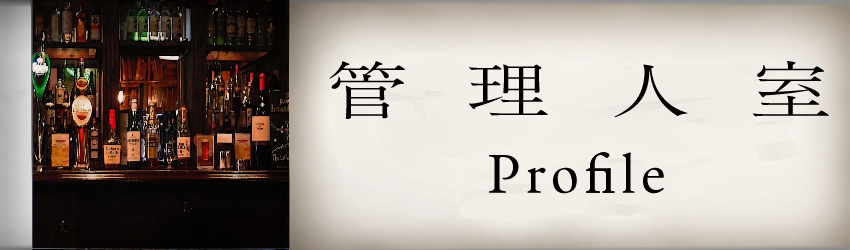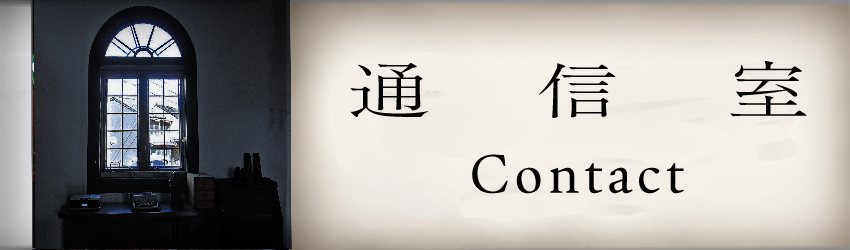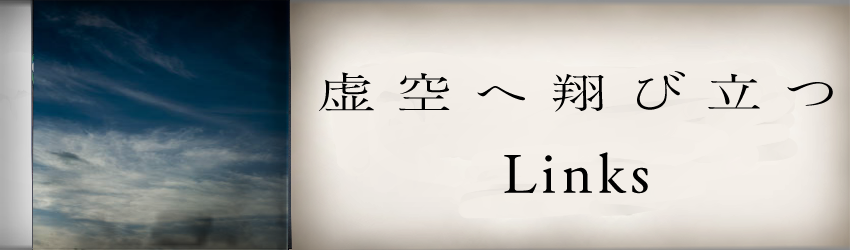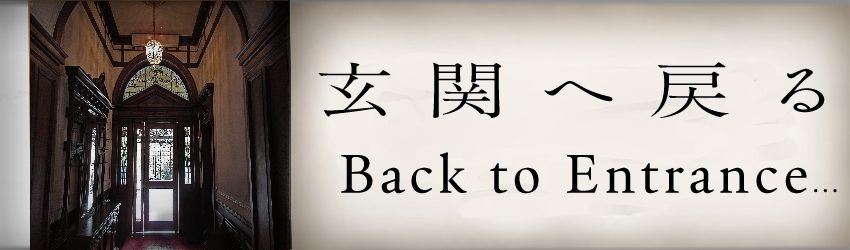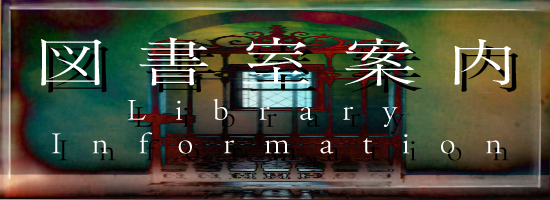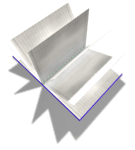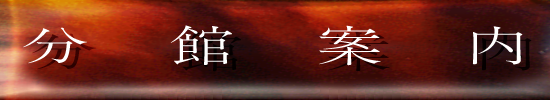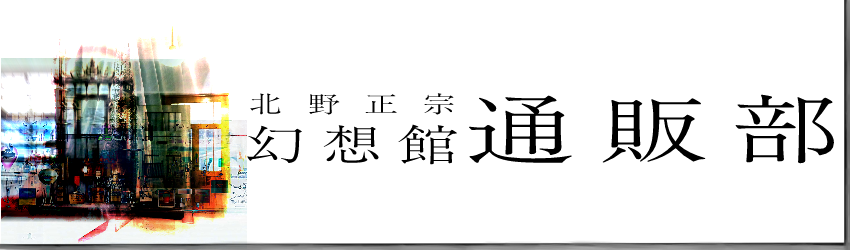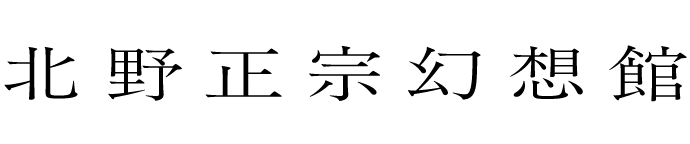※数ヶ月前の眠れない夜、衝動的に、ほんの一時間で書いた物語です。私は普段、こういうことばかりを考えていますよ、という文です。もちろんフィクションですが、けっこう現実の私とリンクしていたり。つたない部分はご愛嬌。
----------
Ⅰ
ぼくは何故か、服を着られない。
着たくても、着られない。
頑張って着たつもりになっても、周りからは笑われっぱなし。
つまり、着たつもりになっているだけで、着れていない。
ぼくは、生まれてからずっと、はだかのままだ。
みんなが、ぼくのことを、馬鹿げた存在として扱う。
ぼくがはだかであることが、ひどくおかしいらしい。
あなたは、ぼくを実際に見たら、びっくりするかもしれない。
ばかげたやつだと、まともに取り合ってくれないのかもしれない。
けれど、ぼくは必死だ。
着たくないんじゃない。着られない。
好きでこうしている訳じゃない。
どれだけ無理をしても、着られない。
周りが無理矢理着せようとしても、何故かいつも失敗に終わる。
決して、抵抗している訳でもないのに。
つくづく、自分を、覆い隠せない。
だから、ぼくはずっと、自分を晒して、生きなければならない。
当たり前だけれど、全く周囲に溶け込めない。
どこにいたって、すごく浮いている。目立つ。
色々な人に注目されて、すぐに目をつけられる。
もちろん、嫌で嫌で、たまらない。
注目を集めて、碌なことになるわけがない。
けれど、どうにもできないんだ。
ぼくのこと、変なやつだと思ったでしょう。
ぼくも、そう思う。
ぼくの周りのみんなは、一人残らず、ぼくのことを、きちがいだと嘲笑う。
とても、人間扱いはしてくれない。
けれど、本当に、そうなのかもしれないという考えが、頭をかすめる。
ぼくは、ぼくを人間扱いしないみんなを、決して否定できない。
辛くてたまらない筈なのに、納得してしまう。
やっぱり、変だと思うでしょ?
こんなきちがいの言うことだから、別に、まともに取り合ってくれなくたっていい。
馬鹿な冗談だと、嘲笑ってくれれば、それでいい。
けれど、もしも君が、ぼくの言葉を、そのまま、真摯に受け止めてくれるのだとしたら。
ぼくにとって、それ以上の救いは無い。
Ⅱ
ぼくは、考えることが、好きだ。
いろいろなことを、ずっと深くまで追いかけて、決して到達出来ない真理を目指して、無限に突き詰めるのが、大好きだ。
そうでもなければ、ぼくは、もうとっくに、自分に耐えきれなくて死んでいたに違いない。
だって、ぼくは、考えることをやめられないから。
ぼくのもつ思考は、どこまでも強迫的だ。
もはや、呪いの類なのかもしれない。
ずっと考えていないと、ぼくは、自分を保てない。
だから、いつだって、どれだけ追い詰められて余裕が無くたって、考えることだけは、絶対にやめられない。
このことは、ほとんどの人たちには理解できないと思う。
多分、ぼくと同じしくみで動いているごく少数の人にしか、わからないんじゃないだろうか。
だからこそ、ぼくの発する言葉は理解されずに、多くの場合は軽い冗談だと思われて、笑われたり、人を馬鹿にするなと怒られたりする。
お父さんなんか、特に酷い。ぼくが勇気を振り絞ってこういう話をしたとしても、「おまえ、暇なんだな。だらけてるからだ。もっと別のことで頭を一杯にしろ」って一蹴する。
理解してくれないとは言ったけれど、ぼくは、理解してもらうこと、共感してもらうことまで望んでいるわけじゃない。
ぼくは、ぼくの言葉を、冗談だとあしらわずに、真面目に受け止めてほしいだけなんだ。
ただ、そのまま受け止めてくれる、それだけでいいのに。
みんな、ぼくの言うことを、ばかげた戯言だとしか考えてくれないんだ。
決して、見捨てられるようなことはなかったけれど。
それでも、誰一人、まともに取り合ってはくれない。
ぼくは、それが、たまらなく悔しくて、寂しくて、悲しい。
だって、ばかげた戯言だと一蹴される、その言葉こそが、ぼくだから。
ぼくは、みんなから見れば、戯言のようにばかげた存在だということだ。
それが、悲しくないわけがない。
ぼくは、一生懸命に、必死に、生きている。
そこは、みんなと、決して変わらないはずなのに。
そういうわけで、ぼくは、物心のついた時から、自分をないがしろにされている、まともに取り合ってもらえないという悲しさと寂しさにまみれていた。
“あの人なら、この人なら、ぼくのことを受け止めてくれる”という淡い期待を抱いては、何度も裏切られてきた。
そのたびに、胸が張り裂けそうになったけれど。
それでも、以前のぼくは、未だに人間を信じることをやめていなかった。
いつかは、いつかは、誰かひとりだけでも、自分を受け止めてくれると、信じていた。
その頃のぼくは、あまりにも、生きることに苦しんでいた。
純粋で、健気だった。
だからこそ、とてつもなく愚かだった。
あろうことか、ぼくは、自分の生命線である思考を、自ら断ち切ろうとしたんだ。
Ⅲ
あの頃のぼくはまだ、わかっていなかった。
自分が、思考を止めると壊れてしまう人間だと。
死ぬまで思考を止められない人間だと。
だから、何かで猛烈に忙しくなって、考えることをすべて頭から締め出してしまおうとした。
荒療治だけれど、そうすれば、辛いことも考えずに済むと思った。
そうして、ぼくは、自分の思考から逃避するために、勉強に依存した。
どれだけ変な人間でも、一番求められていること、つまり勉強さえ出来ていれば大丈夫だと、けなされたり、嘲笑われたりすることは無いと、そう信じていた。
強迫的な思考から逃避するためには、当然、その手段である勉強も強迫的になった。
並の勉強量では到底思考を締め出せなかったぼくは、無意識のうちに、どんどん勉強量を増やしていった。
それだけ、辛い日常について考えることから逃げたくて仕方なかった。
最終的に、ぼくは、睡眠時間を全て削ったばかりではない。
どんな僅かな時間ですら、ひたすらに脳内で勉強の内容を唱えるようになった。
ついには、ベッドに入っても自分が寝ているんだか起きているんだかわからず、何も意識していないはずなのに、勉強の内容が脳裏を飛び交っていた。
あきらかに自我が分離していた。狂っていた。
それでも、自分の中から思考を締め出すのは、到底不可能だった。
当然だ。生きている内に、自分の生命線を締め出せるわけがない。
そんなの、自殺行為だ。
死、まさにそのものだ。
だから、ぼくの勉強も、過労に重なる過労によって、ついに死に到達するかもしれなかった。
今になって思えば、その方がましだったのかもしれない。
そうすれば、完全に自分から逃げ切り、目的を達成したことになったのだから。
けれど、そうはならなかった。
一度目の過労に達した時点で、ぼくは体をひどく壊し、まともに勉強することが出来なくなった。
それ以前とは比べ物にならない地獄に堕ちた。
そうして、ぼくはようやく理解したんだ。
もう、死ぬまで、思考の呪縛からは逃れられないということを。
そして、そんな単純なことにも気づかずに安易な行動をしていた自分が、今の今まで、人間に夢を抱き、どこかで信じていた自分が、目も当てられないほどに愚かであったということを。
Ⅳ
ぼくは、急に全てが抜けたように空っぽになった。周囲の人間が何をしようとも、一切反応しなくなった。
両親は、ぼくの勉強を禁止し、精神科に通わせだした。
ぼくが、遂に心を壊したのだと考えたらしい。
確かに、世間から見ればそうなのかもしれない。
けれど、ぼくにとって、むしろこれは、正常な自分への復帰にほかならなかった。
ぼくは、生まれた時から獣だったのだ。
何たることだ。夢に魘されて狂った獣であったのだ。
耐え難い仕打ちを受けながらもなお、人間を信じ、甘い夢の中にあった今までが、狂っていたのだ。
ぼくは、ようやく、夢から覚めた。
夢に生きる力を、人間性を喪失した。
生涯にわたって現を見ることが叶わず、夢の中で踊り続ける、人間だけが持つ愚かさを失った。
それだけのことだ。
けれど、その裏返しも、生きる力も、失った。
人間性を失ったぼくは、人生という、愚かしくも素晴らしい道から凋落してしまった。
ぼくは、もう、人間でも獣でもなくなってしまった。
現の世界に、自我を、夢を持ち込んでしまった。
夢とは、決して現に移し替えてはいけない植物である。現の土に植え替えた途端にその玉虫色の葉は萎び、虹色の花弁は散って、赤黒く醜い肉塊と化す。
そして、その花、はもう二度と咲かなくなる。
ああ、なんということだろう。ぼくは、ぼくの夢を殺してしまった。
もはや空想の中ですら、私が恍惚を抱くことはない。
ぼくは少しずつ自分の夢を潰し、自分自身を殺してきたのだ。
それに気づいた瞬間、生きる気力がすべて削がれてしまった。
もう二度と、生きたいとは思えなくなってしまった。
Ⅴ
ぼくは、一体どうして、物心がついた時から、自分が人間だと錯覚していた?
どうして、ぼくはかつて、人間として夢の中に生き、人間として、人間を信じ、愛することが出来てしまっていたんだ?
そんなことは、今となってはどうでもいい。
どちらにしろ、もう、駄目なんだ。
一度、人間として、夢の中に生きてしまったから。
人間が抱く幸せを、その尊さを、知ってしまったから。
もう、現に、ただの獣としては、生きられない。
夢に、ただの人間としても、生きられない。
現に生きる獣でありながら、絶対に手に入らない、人間の幸せを、夢を求めて、生きていく。
地獄。
まさに地獄である。
やはり、今のぼくは、もう人間とは呼べない存在であろう。
人間は、全員が精神病者だ。生まれてから死ぬまで、一生を夢の中に過ごす生き物だ。
ずっと、人間を信じ、それによって幸せを追いかける生き物だ。
幸せだって、人間だけが抱く、夢に過ぎないんだ。
だから、人間を信じなくなった今のぼくは、夢を殺し、現に立った今のぼくは、獣だ。
決して、人間が現に生きることなんて、あり得ないんだ。
現に立ったぼくは、人間を信じることを、やめた。
自分のことを一番に考えてくれている、育ての両親でさえ。
当然だ。人間共が大切に思っているぼくは、全部、ぼくが作り出した嘘なんだから。
誰一人として人間を信じられないぼくは、本当の孤独の中にいる。
あなたはまだ、きっと、知らないだろう。
本当の孤独のおそろしさを。
本当に孤独な存在は、絶対に、幸せになんかなれない。
このことは、ぼくが、一番よく知っている。
もしあなたが、そんなことはない、ひとりでいるのが楽しい、引きこもることが好きだ、自分の為に生きることが幸せだと感じられるのだとしたら、おめでとう。
あなたはまだ、十二分、幸せになれる可能性がある。
人間だからだ。
夢を抱けているからだ。
今の時点でも、少なくとも、ぼくほど不幸ではない。
あなたは、あくまでも、ひとりでいるふりをしているだけだ。
そんな考えが浮かぶ時点で、あなたは、少なからず夢に生きている。
人間を信じて、そこに自分を委ねられている。
本当のひとりぼっちでは、孤独では、決してないよ。
だから、あなたは、大丈夫。
けれど、ぼくは、本当にひとりぼっちだ。
本当に、孤独なんだ。
夢を、人間を愛しながらも夢から締め出され、獣になった。
人間を、一切合切、信じられなくなってしまった。
ぼくは、もう、自分を、誰かに委ねられない。
自分の為にしか、生きられないんだ。
自分しか、生きる理由に出来ないんだ。
何をしても、どこまで走っても、挙げ句の果てに死んだとしても、結局全て、自分の為にしかならない。
あとには、ぼんやりとした虚しさしか残らない。
そんな中、たったひとりで、自分だけを、命がけで守らなければならない。
何があろうと、他人を生きる理由に出来ない。
他人の為に、生きてはゆけない。
だから、幸せを感じられない。
幸せを知りながらも、絶対に、幸せになれない。
これ以上に辛いことを、これ以上の不幸を、地獄を、ぼくは知らない。
もしも、本当に夢から覚めないで、人間のふりをしたままでいられたら、それとも、最初から夢など知らず、ずっとただの獣として生きていられたなら、どんなに良かったことだろう。
人間として物心がついてから、ぼくは、ずっと裏切られ続けてきた。
それでも、誰かを好きになりたかった。
誰かを、たったひとりだけでもいいから、心の底から信じて、ぼくを委ねたかった。
そうして、その人が背負った分だけ、ぼくも、その人を背負いたかった。
自分ではない誰かを、命をかけて守りたかった。
その人と共に在ることを、生きる理由にしたかった。
その人の為に、生きたかった。
幸せに、なりたかった。
ーーーーーーーーーー
元記事投稿日 – 2024.11.28 13:38