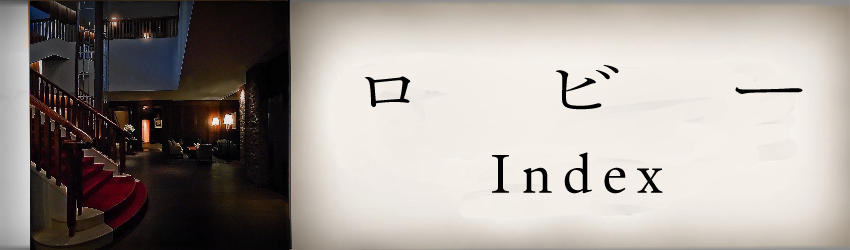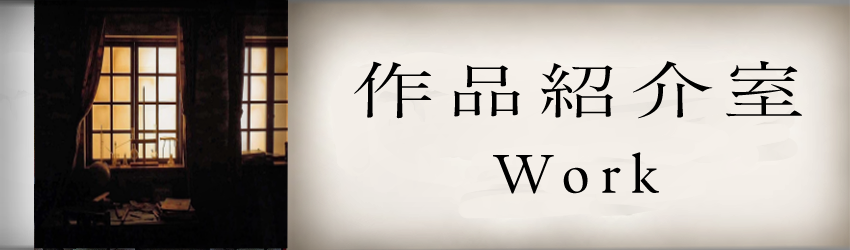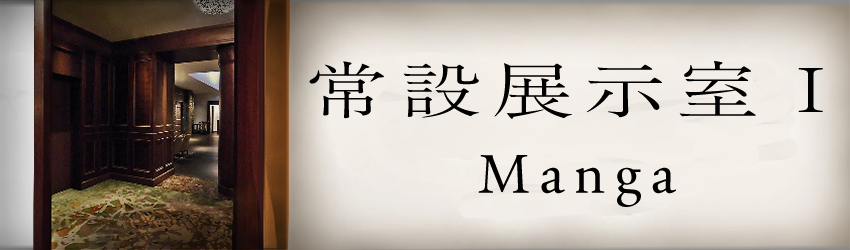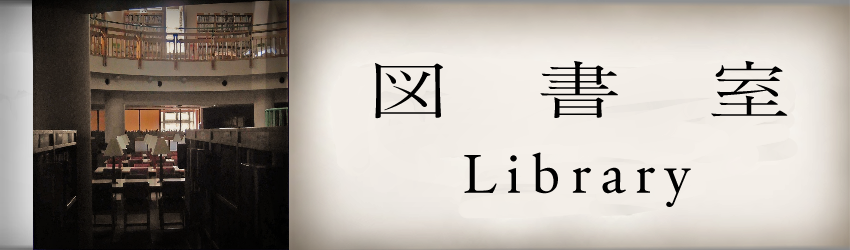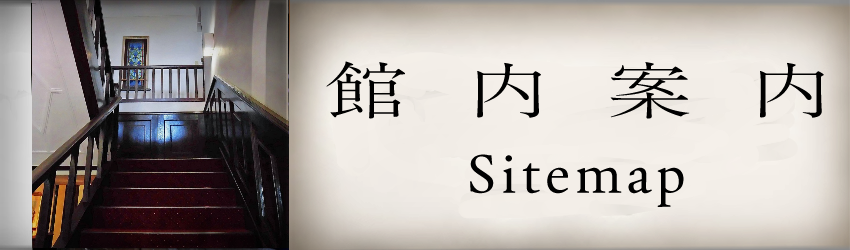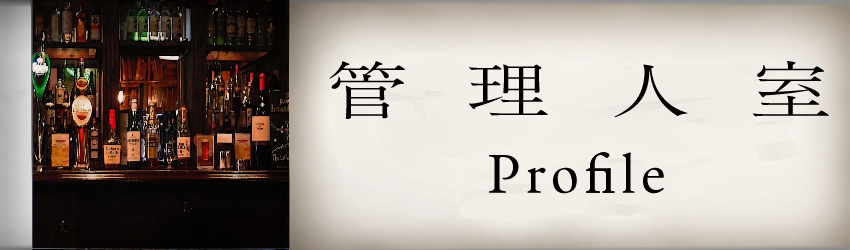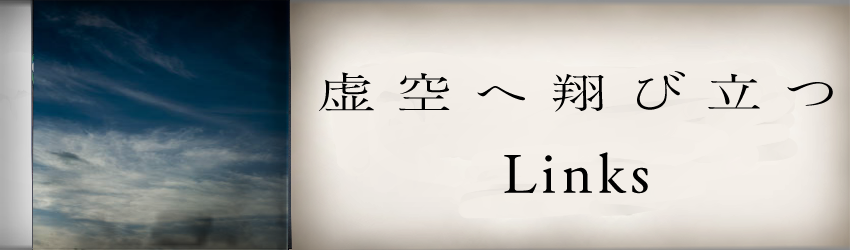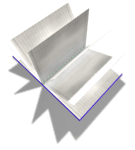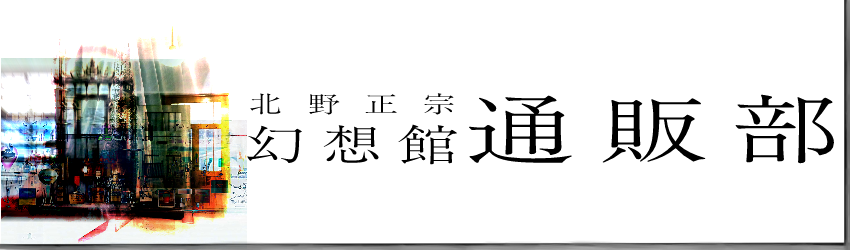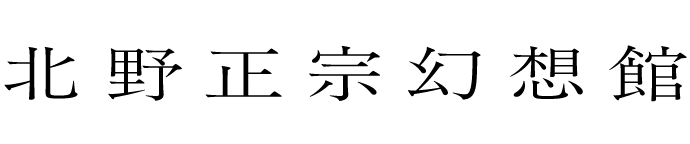補足(2025年8月23日深夜):こちらの記事は、現在のホームページ(北野正宗幻想館)の前身の前身(masamunekitano2007.wordpress.com、現在は閉鎖)にて投稿された、私にとって2番目のブログ記事です。
その点をご了承いただいたうえでご覧下さい。
私に、親友が出来た。
ほんの一週間程前のことだ。
それまで、友達と呼べる存在すら、まともに持ったことが無かった自分である。そんな自分に、急に、一切をかなぐり捨てて信頼し、自分の心を委ねられるほどの親友が出来たのだ(正直、もはや親友という言葉で形容しきれるか怪しいが、その彼は私を親友と呼んでくれているので、ここでもそう呼ぶことにする)。
彼と出会ったのは、半年以上前、今年の4月、進級して新しい専門コースに配属された時だった。
名前順の席で、たまたま、私の前が、彼だった。
人数が多い場所だったこともあって、人間嫌いの私は嫌悪に顔をゆがめ、他者に話しかけられないように、他者が、出来る限り自分から離れていくように、必死に、心の中では泣きそうになりながら自分を守っていた。そんな状態の私に、彼は臆することなく話しかけてきた。
はっとして顔を上げた私は、彼の表情を見た時、なぜか確信した。
してしまった。
彼になら、彼になら、私を曝け出しても大丈夫かもしれない。そのまま、そのままで、受け止めてくれるかもしれない、と。
こんなことは、本来、有り得ないことだった。
けれど、それだけ、彼の表情は無垢だった。
それまでに出会ったどんな善良な人間からも、幼い頃はまだ最も信じていた母親からでさえも少なからずにじみ出ていた攻撃性というものが、まるで見当たらなかった。
人間である筈なのに、全く表裏が無く、内面が全て外部に筒抜けになっているかのように見えた。
”彼がサイコパスで、外面だけは素直なふりをしているが、実のところ内面はどこまでも残酷なのだ”という普段の自分なら思い浮かびそうな考えも、はなから思い浮かばなかった。
こちらを見下したり、嘲笑したり、探りを入れる様子なども、全く無かった。
本当に、純粋に、自分とかかわりを持ちたい、ひいては仲良しになりたい、それだけを考えているとしか捉えられない程に、無垢な視線だった。
彼は、たしか丁寧に自己紹介をしてくれていたと思うのだが、正直、呆気にとられ過ぎて、彼の話した内容は、ほとんど頭から滑り落ちてしまっていた。
私も名を名乗るくらいはしたと思うのだが、それも、ほとんど反射的な、無意識の内の行動だった。
ただでさえ人間を信じられなかった当時の私に、こんなに素直な人間がこの世に存在することが、信じられるわけもなかった。
変な言い方だけれど、彼の言動の全てに、聖母のような包容力があふれていた。
天使だと、無意識のうちに、そう感じた。
彼はきっと、人間ではない。
”本当なら天上で暮らしているはずの本物の天使が、何かのいたずらか間違いでこの教室に居るだけだ”と、そういうバカげた妄想で事を片付けたくなってしまうほどに、当時の私は人間不信だった。
しかし、これほどまでに頑固な私でも、彼にはとうとう屈さざるを得かった。
彼のことは、疑うこと無く一切合切信じざるを得なくなってしまった。
初めて出会ったその日から数日も経たぬうちに、そんなことを考えるのはとても失礼なことだと思うくらいに、汗を流して、一生懸命に生きている彼の姿を目の当たりにしたからだ。
ここまで無垢でありながら、彼は、まごうこと無き、本当に生身の人間であった。
一体、何をどうしてそうしたら、そんな人間が育つというのだろうか。
もはや、奇跡としか考えられなかった。
何よりも人間を信じたくなかった、信じられなかった当時の私が、それでも信じてしまった、たったひとりの人間。
この時点で、私にとって、彼は、十分特別な存在になっていた。
彼は、それからほぼ毎日、私に話しかけてくれていた。
席が変わって離れても、私の席まで話に来てくれていた。
嬉しかった。本当に、泣きたくなるほど、嬉しかった。
そういう気遣いをしてくれる人間は、思い出せる限り、家族以外で初めてだった(第一、進学後は家族とも離れて生活しているので、そんな存在は本当に身近にいなかった)。
けれど、つい最近までの私は、そんな彼に、一言、二言しか、返せなかった。
わからなかった。
本当に、どうすればいいのか、全く分からなかった。
彼が一生懸命に何度も語り掛けてくれても、すぐに会話が途切れた。
なんとか会話を繋げようとしても、無理矢理にこじつけるせいで、私の言動はものすごく不自然なものになっていた。
はっきり言って相当に浮いていたし、そんな私の傍にいる彼も、相応に奇異な視線を周囲から向けられていたと思う。
それでも、私はずっと、ぼくのところに来てくれていた。
話したかった。
いつもの雑な偽りの姿、自分を守る為に必死に戦っている姿じゃなくて、何にもおおわれていない、本当の自分を曝け出した姿で、彼と話したかった。
ずっと、ずっと、そればかりを考えていた。
けれど、それを分かっていながらも、私は自分を開くことが出来なくて。
結局、その状態が、半年以上続くことになった(あとから彼にそのことを謝った際、彼はむしろ喜んでいると語った。彼は、ぼくが心を開くのに、普通にこの先数年はかかると考えていたらしい)。
以前の私は正直、結構な辛い思いをして、日々を過ごしていた。
周囲の皆が、私のいないところで、私をきちがいだ、障害者だとあざ笑っていたことを、ぼくは知っている。
だからと言って、私のいるところでは大丈夫かと言われれば、そんなことも決してなかった。
私は、中学に入るまでは、やはりそこそこいじめられた。詳しい内容はここには記さないでおくが、正直、そのうちの大半は親にも教師にも言わず、ひっそりと孤独に抱え込んだままに終わった。
いじめっ子からの報復が怖かったとか、そういう理由ではない。
周囲の子供たちがいじめを吐露して、その後に大人たちや同級生から手厚く守られているのも、この目で何度も見て来た。
それでもなお、私がいじめを吐露できなかったのは、そもそも、親や教師を、信じることが出来なかったからである。
親や教師ばかりではない。
友人(こっちは全くそう思っていないのに、彼らからは勝手にそう思われていたらしい)人間たち、同級生、近所のおじさんやおばさん、親戚、家族、道ですれ違う、名前も知らない通行人に至るまで。
私は、人間というものを、信じられなくなっていた。
私が、人間を信じなくなったのは、信じられなくなったのは、物心がついてからずっと、人間を信じた以上に、裏切られたことのほうがずっと多く、ずっと心に残っているからだ。
正直なところ、私は今でも、自分をきちがいだとか、障害者だとか思ったり、声に出して呼ぶ周囲を、全然否定できない。
私を人間扱いしていないとわかっていて、辛くてたまらない筈なのに、むしろ、それに納得してしまうことの方が多い。
昔から、そうだった。
そのくらい、自分が周囲の大多数の人間から逸脱した傾向があることを、私は知っている。
注意:これから示す傾向は、もしもあなたや周囲の人が持っていたとしてもけっして卑下するべきものではないし、これらに対する差別は非人間的で、断固として許されるべきものではない、差別主義者は悪魔であると現在の私は断言する。しかし、かつての私は、幼少期より、これらの傾向により自分が周囲から見ると変わっていること、外れ者扱いされることにより、自分を酷く卑下し、自責の念に追われ、実際に死を思ったことも、決して少なくはなかった。
幼少からずっと、強迫性障害の傾向は抜けなかった。
小学校に入学してすぐ、ランドセルのふたがロックされているかが不安で、数十分間ずっとロックを確認していて、母親に叱られた。
毎日、寝る前に玄関の鍵が閉まっているかが不安で、よく眠れなかった。
右足にかけた分の体重だけ、左足にもかけながら歩かなければならない、この色のタイルの上だけを歩かなければならないなど、意味不明な、明らかに不必要なルールを自分で自分に課し、守れなかったときのことを考えると死ぬよりもよほど恐ろしかった。
幼少期、ほぼ間違いなくギフテッドであったことは、母親も認めるところである。
幼稚園のころからずっと、文系、理系問わずあらゆる勉学に対して、非常に優秀であった。
また、芸術的なセンスは同年代の子よりもずば抜けて高く、図画工作の授業では毎回一人だけとびぬけた作品を制作し、周囲をひどく驚かせた。
とても高い集中力も持ち合わせていた。
他にも様々な影響があったのだろうが、一部の発音が上手くできずに、幼稚園から小学校低学年頃まで、発語教室に通っていた。
一般に残虐、グロテスクに分類される写真や絵画、動画を見ても、全く嫌悪感を覚えず、むしろそれが好きで、いつしかこぞって見るようになった。
逆に多くの人がそうした事物に対して覚える生理的な嫌悪感、気持ち悪さを、女性の膨らんだ胸や尻に覚えた。
同性愛者であることは、正直、それらの中でもかなり大きな影響を占めていた。
自分でもはっきりと自覚しやすいことだったし、なにより、その傾向は、どれだけ覆い隠そうとも実際の言動に強く現れる、抵抗のしようがないものだった。
幼稚園に通っていたころから、人体図鑑で、筋肉の動きを示す男性ヌードモデルの写真を見るたび、明らかに異様な感情を覚えた。
常に意識していないと女口調になってしまうから、両親によく叱責され、矯正されていた。
周囲の男の子が興味を示すかけっこ、鬼ごっこ、海水浴、虫取りには全く興味を示さず、独り、家や教室で本を読み、絵を描き、裁縫をし、編み物をしていた。
母親が若い頃に購読していた女性向けの手芸雑誌が大好きで、2階の部屋から引っ張り出してよく読んだ。
母親の使う花柄のハンカチや服、アクセサリー、化粧道具にひどくあこがれた。
男の子とはやはり馴染めなくて、女の子たちと、まるで同性であるかのように馴染み、一緒にいた。
プールの男子更衣室でひとりだけ顔を赤らめ、女の子のように首から下をタオルで覆い隠し、恥ずかしそうに着替えをしていれば、同性愛という概念を知らずとも、みんな、大体のことは察するものである。
これらの傾向も、当時かなり大きく影響していたのであろうと思う。
けれど、なによりも私は、考えることが好きな人間なのだ。
日常で出会うあらゆる物事について、ずっと深くまで熟考して、絶対に辿り着けないと理解していながらも、その”真理”を目指して、永遠に突き詰めていく、その行為が、生命活動以外では物心がついたときからずっと続けている唯一の行為である。
その行為が好きだったからこそこういう人間になったのであろうと思うし、もしも好きでもないのにこうなったのだとしたら、ぼくは、もうずっと前に死んでいたに違いない。
つまり、どこまでも思考することこそが、私の生命線であり、同時に呪いなのだ。
生命線だから、これがなくなると、私は確実に壊れてしまう。
二度と、私ではなくなってしまう。
ずっと、ずっと考え続けていないと、私は、自分を保てない。
私のもつ思考というものは、どこまでも強迫的なんだ。ひょっとしたら、強迫性障害の傾向を持つ原因も、ここにあるのかもしれない。
いつだって、どんなに追いつめられていたって、死にかけていたって、私は、強迫的に考えることだけは、絶対にやめられない。
そういうしくみで動いている人間なんだ。
本当に、生命線でありながら、呪いそのものだよ。
こういう人間は、正直、だいぶ少ないと思う。
いや、私以外に一人たりとも居ないとは、全然言うつもりは無い。
けれど、少なくとも私の周囲には、信じられない程に少なかった。
だから私の言葉は全て、その突き詰めに突き詰め、突き詰めた挙句の果てに生まれた、熟考の産物なんだ。
だからこそ、同じようなしくみで動いている人間には理解される、されなくても、少なくともまともに受け止めてもらえるけれど、そうでない人間には、びっくりするくらいに理解されないし、まともに受け取ってもらえない。
だから、ぼくの発する言葉は幼い頃からずっと、周囲からまともに取り合ってもらえたことが、全くと言っていいほどに無かったのだ。
周囲の人々は、例外なく、ぼくの言葉を、軽い冗談だと考える。
だから、笑われたり、馬鹿にされたり、あるいは、人を小馬鹿にするなと怒られたりする。
父親は、正直、特にひどいよ。
私が勇気を振り絞ってこういう話をしたとしても、「おまえ、暇なんだな。だらけてるからそういうくだらないことしか考えないんだ。もっと必要な、別のことで頭を一杯にしろ」って一蹴する。
私は、ただ、ぼくの言葉を、冗談だとあしらわずに、真面目に受け止めてほしいだけなんだ。
私、そのまま受け止めてくれる、それだけでいいのに。
みんな、私の言うことを、ばかげた戯言だとしか考えてくれないんだ。
決して、見捨てられるようなことはなかったけれど。
それでも、誰一人、まともに取り合ってはくれない。
だから、ぼくは自然と、私を普通に見せる、カモフラージュさせるスキルを、生存本能的に身に着けざるをえなかった。
自分が馬鹿にされないように、必死に作り上げた安っぽいハリボテには、みんなが真面目に、真摯に接してくれた。
そいつの発する言葉をまともに聞いて、そいつのことは、優秀だ、秀才だとほめたたえてくれた。
私は、それが、たまらなく悔しくて、寂しくて、悲しかった。
だって、ハリボテの隙間から時折のぞく、くだらない、ばかげた戯言だと一蹴される、その言葉こそが、本当のぼくだから。
つまり、本当の私は、みんなから見れば、戯言のようにばかげた存在だということだ。
それが、悲しくないわけがない。
私は、一生懸命に、必死に、生きている。
そこは、みんなと、決して変わらないはずなのに。
それなのに、私は、常に冗談扱いされる。
自分という存在、そのものを。
”この人なら大丈夫だ、死なない為に作ったこんな安いハリボテじゃなくて、その中の、本当の私に真摯に接してくれる”という淡い希望を抱いて他人を信じては、裏切られた。
最初のうちは、幼いうちは、それでもまだ、人間を信じていた。
何度裏切られたって、訴えかけ続ければ、いつかきっと、わかってくれるって。
本当の自分と、きちんと向き合ってくれるようになるって、信じていた。
でも、そうはならなかったんだ。
何度も、何度も、数え切れないほどにそれを繰り返す内、私は、すっかり疲弊してしまった。
人間に、絶望した。
だから、人間を信じることを、やめた。
同時に、人間を信じることが、出来なくなった。
そんな風に、辛い日々を過ごしていた中学の頃。
ぼくは、今と比べればまだ純粋で、すごく健気だった。
だから、この辛い日常から逃げようと、きっと、逃げることが出来ると、無意識の内に、そう思い立った。
辛さのすべての原因は、楽しかったはずの、強迫的な思考であると、そう結論づけた。
これさえなければ、強迫性障害にも、ゲイにも悩まずにすむ。
そもそも、他の人と同じになれる。
他の人と同じ考え方になって、みんなが、自分そのものを、まともに取り合ってくれるようになると考えた。
あまりにも愚かである。
そのために、当時の僕は、あろうことか、自分の生命線である強迫的な思考から逃げ、あわよくば、それを自分から締め出そうと行動し始めたのである。
そのときの僕は、自分がどういうしくみの人間かを、理解出来ていなかった。
強迫的な思考こそが自分の生命線、ひいては自分そのものであり、それがなければすべてが壊れてしまうから、絶対にそれからは逃れられないなど、気づいていなかったのである。
そうして、ぼくは、逃避の手段として、勉強を選択した。
この逃避行の目的は、ひいては周囲が自分にしっかりと向き合ってくれるようになること、つまり、周囲が今の自分に一番求めていること、勉強は、そのためには最も手っ取り早い手段である。
しかも、先述の通りにギフテッドの傾向があったため、それまでも、勉強はそこそこ優秀だった。
それに、ゲイだったり、社会生活を送る上で不安なことはたくさんあるけれど、勉強さえできれば、なんとかなるかもしれないという希望もあった。
これ以上にに合理的な選択肢は、当時の私には思い当たらなかったのだ。
強迫的な思考から逃避するためには、当然、その手段である勉強も強迫的になった。
並の勉強では到底強迫的な思考を締め出せなかったぼくは、無意識のうちに、どんどん勉強の量を増やしていった。
今だから、こんなふうに細かく分析してまとめられているけれど、正直、当時の僕は、ここに書かれていることなんてまったく頭になかった。
これから書くことも含めて、ほとんどが無意識中の、言ってしまえば、生きる為、死なない為の思考、行動であった。
それだけ、自分の特異性について考えざるを得ないこと、本当の自分が他者にまともに取り合ってもらえないと感じることが、辛かった。
生きることが、辛くて仕方が無かったのだ。
最終的に、私は、睡眠時間を全て削ったばかりではない。
登下校時はおろか、便所に行くとき、席を立つとき、頭をかくとき、そんな、日常生活の極僅かな時間ですら、ひたすらに脳内で勉強の内容を唱えるようになった。
はっきり言って、学校のテストで満点を取るのにも必要のないことまでやっていた。
それでも、自分の中から強迫的な思考を締め出すのは、到底不可能だった。
当然である。強迫的な思考が自分から締め出された暁には、死よりも余程恐ろしいことが待っている。無意識の内に、生存本能がそうさせないように必死に守っているのだから。
けれど、そんなことは微塵も知らない当時の私は、さらに強迫的に、勉強に依存していった。
正直、この段階まで来ると、麻薬中毒と同じレベルで依存しているといえる。
もはや、それがないと、生きていけないレベルに達しているのである。
だから、私の人生も、ひょっとしたら、勉強のし過ぎによる過労死で、ぱったりと終わりになるかもしれなかった。
親友に出会う前の私は、正直、そのほうが楽でよかったのに、と考えていた。
だって、死んでしまえば、生命線である強迫的な思考を維持する必要は当然無くなるから、完全に自分の中からそれを追いやり、目的を達成したことにはなった筈なのである。
まあ、死んじゃうけれどね。勿論。
けれど、そうはならなかった。
一度目の、まだなんとか死なないレベルの過労に達した時点で、両親が私の異変に気付き、歯止めをかけたのである。
そのときの私は、本当に狂っていたと、今でも思う。なんと、過労の末、手が金縛りに合い、ペンを握っても、涙があふれるばかりで、何も書けなくなってしまったのである。きっと、これ以上勉強をすると死ぬと脳が判断して、阻止する為に信号を出していたのだろう。
もう思い出せないくらいに本当に久し振りに涙が出て来て、ここに来て、私はようやく、自分がおかしかったことに気が付いたのだ。
同時に、自分のことも、正しく理解したのだ。
もう、死ぬまで、強迫的な思考の呪縛からは逃れられないということを。
そして、そんな単純なことにも気づかずに安易な行動をしていた自分が、目も当てられないほどに愚かであったということを。
それからの私は、私を守ろうとした両親によって学校に行くことと全ての勉強を禁止され、強迫的な思考から逃避する術を失ったので、その重圧に耐えきれず、心を壊した。
この鬱の期間が、これまでの人生において、間違いなく最もつらい期間であったと私は断言できる。
それまでも十分に地獄であったが、あの期間だけは、それらとは比べ物にならない程に苦しかった。
正直、死ぬ何十倍も辛かったと思う。
この辛さを表現するのにふさわしい言葉を、残念ながら私は持ち合わせていない。
自分の語彙力の無さが情けないが、正直、あの辛さは、言葉で表現できるレベルをとうに超えていると、今でも思ってしまう。
また、正直、あの鬱の期間のことは、既にあまり覚えていない。
思い出そうとしても、その部分がすっぽりと抜け落ちている。
おそらく、脳のセーフティー的な役割によって、無意識の内に忘却させられたのだと思う。
そういう訳で、申し訳ないけれどここには、その後、数えきれないほどの悶着がありながらも、家族や当時の中学校の担任、以前からお世話になっていたお寺の和尚さん、精神科の医師やカウンセラーさん等の尽力のおかげで、なんとか回復できたこと。その過程で自分の持つ逸脱した傾向や、他人にまともに取り合ってもらえない点等についても、向き合い、ある程度は受け入れることができたこと。残りの分に関しても、それから現在に至るまで、ゆっくりと、少しずつ向き合い、受け入れ、共に生きることが出来るようになったということのみを記しておきます。
あとは、現在でも完全に回復したわけではなくて、薬は飲み続けているし、拒食症や双極性障害が後遺症として残っていて、それに苦しんでいることも。
かなり省略する形になってしまって申し訳ないけれど、正直、鬱になり、そこから回復して、現在の学校に進学するまでの期間は、どうしても書けないことも、書きたくないこともかなり多いので、ご理解いただけるとありがたいです。
とにかく、私は晴れて、現在の学校に進学することが出来ました。
現在の学校は、普通高校ではありません。専門学校で、家から遠いので、私は寮で生活をしています。
この学校に決めた理由は、いろいろあります。
まず、先述の諸々によって、おそらく普通高校での生活には耐えられない、きっと、卒業まで持ちこたえられずに不登校になってしまうと自己判断したことが一つ。
次に、鬱から回復したばかりで、正直、まだ勉強をするのが怖くて、受験勉強をせずとも、それまでの成績と、面接試験のみで進学できる推薦入試のある学校だったというのが一つ。
あれだけ勉強をしていただけあって、流石に成績は最高レベルでしたから、担任の先生と自薦文を夜遅くまで書き、校長先生と面接の練習をして、あとは実際の面接試験を受けるだけで合格できました。
最後に一つ、正直、自分にとっては一番重要だったのが、寮がある、、、まあ、下宿でもアパートでも良かったのだけれど、親とある程度離れて生活が出来ること。
鬱の経験を通して、私は、私のことは勿論、思っていた以上に両親のことを全然知らないということに気づいたし、両親も、少なからず、ぼくのことを全て知っている気でいたけれど、実はあまり知らなかったということに気づいたのです。
その原因は、間違いなく、お互いの距離が近すぎることと、少なからず、お互いに思っていた以上に深い共依存の関係にあったこと。
だから、家族だからこそ、距離がすごく近いからこそ、あえて線引きをして、距離を話した方が、お互いの為になるんじゃないかと、そう考えたのです。
これをそのまま伝えると普通に怒られそうなので、親には濁して伝えましたが。
そういう訳で、私は現在の専門学校を選びました。
正直、後悔はしていないです。
大変なことも多いですが、少なくとも、病み上がりの現在の自分には、普通高校よりかは確実に合っていると思っています。
だから、進学後の環境に、何か不満があるかといえば、そんなことはなかった。
私の判断を尊重してくれた両親にも感謝している。
正直、勉強に依存する前よりも相当楽に生活できるようにはなった。
けれど、正直、楽になったとはいえ、その前があまりにも辛かったから、、、楽になったとはいっても、十分に辛いのは変わりなかった。
後遺症として残った拒食症や双極性障害はもちろん、強迫性障害や同性愛者であること、相変わらず本当の自分を曝け出せないことも、ある程度は受け入れられたけれど、苦しい時は、すごく苦しかった。
人間を信じていないのは変わらないから相変わらず孤独だったし、毎日が憂鬱だった。
その状態が1年続いて、突然に目の前に現れたのが、彼だったのだ。
純粋で無垢で朗らかな彼は、かなりの人間不信だった僕を、無理矢理にでも信じさせる力を持っていた。
彼と言う人間を、再び信じさせてくれた。
私は、それが、本当に嬉しかったんだ。
私は、ずっと昔から知っていたんだ。
自分ではない、誰かのために生きること、他者を生きる理由にすることを、人は幸せと呼ぶって。
けれど、人間を、他者を信じられない自分には、それができなかった。
私は、幸せになんてなれなかった。
人生のすべてをかけて、自分一人だけを、命がけで守ってきた。
私が、これまでの人生で何よりもつらかったことは、強迫性障害でも、同性愛的性質でも、他者がきちんと向き合ってくれないことでも、勉強への逃避依存でも、拒食症や双極性障害でも、あの鬱でもなかったんだ。
自分のためにしか、生きられなかったことだったんだ。
自分しか、生きる理由に出来なかったことだったんだ。
私は、誰かのために生きたかった。
誰かを、心の底から信じて、愛したかった。
自分ではない誰かを、命をかけて、守りたかった。
その人に、私の片割れを委ねたかった。
そして、その人が背負った分だけ、私も、その人の片割れを背負いたかった。
その人と共に在ることを、生きる理由にしたかった。
その人と助け合いながら、生きていきたかった。
ずっと、幸せに、なりたかったのだ。
彼を始めて見た時、それから話しかけてくれるたびに、思っていた。
彼になら、これまで孤独に、命がけで守ってきた自分を、曝け出せるかもしれない。委ねられるかもしれないって。
その分、私も、彼のことを支えられるかもしれないって。
彼のことなら、心の底から信じて、大切にしていけるかもしれないって。
果たして、それは、そうなった。
一週間ほど前の試験終わり、私は彼に、自分のことを、初めて話した。
何かのきっかけがあったわけではないけれど、話した。
それまで、何よりも大切にしてきた自分のことを、裸の状態で、彼の目の前に晒した。
彼のことを信じていたから、何も臆することは無かった。
私を受け止めるも、そのまま壊すも、完全に彼の自由にした。
私は、二人きりの教室で、何時間も、彼に対して話した。
彼は、私のひとつひとつを、真摯に受け止めてくれた。
そして、そのひとつひとつに理解を示し、多くの言葉を返してくれた。
あの瞬間から、私と彼は、親友になった。
彼は、私に、生きる理由を与えてくれたんだ。
先述の、”人を信じた以上に、裏切られたことの方が多かった”というのは、実は、彼が私のことを表現するために使った言葉だ。
確かに、そうだ。その通りだ。
幼い頃の無垢な私は、人々を信じていたんだ。
みんなは、今はまだ、偽りの自分しか愛してくれないけれど、いつかは、本当の自分に、気付いてくれるって。
いつかは、本当の自分を、愛してくれるって。
けれど、それは、叶わぬ幻想だった。
人々が愛するのは、私が必死に作った、偽りの虚像ばかり。
その隙間から時折本当の私が見え隠れすると、人々はこぞって本当のぼくを糾弾した。
だから、私は、いつしか人間を信じなくなった。
ひいては、人間からここまで糾弾される自分を、人間ではないと考えるようになった。
実際、時折、自分が人間ではない、別のなにかであるという感覚を覚えていた。
自分の外形が怪物同然に醜くなり、人々に恐れられる中で、孤独に狂ったように自分が笑っている場面を想像するようになっていた。
ひょっとしたら、そのまま生きながらえていれば、本当に、人間ではない何かになってしまっていたのかもしれない。
そこから私を救い上げてくれたのも、ぼくを人間側に引き戻してくれたのも、彼だ。
彼は、私は怪物ではなく、人間なのだと教えてくれた。
私も、胸を張って、怪物ではなく、人間として生きていっていいのだと、教えてくれた。
彼は、私の宝物だ。
きっと、ぼくの人生で、一番の実りだ。
彼と出会ってから今日までの間、これほど自分が産まれてきたことに感謝したことは、今までになかった。
これまでの出来事が、全て、彼に出会う為の試練だったのではないかと思える程に。
どれだけ辛くても、彼の為に生きたいと思うようになった。
彼は、私の、生きる理由になった。
彼が、私を助けてくれたように。
私は、それ以上に、彼を助けたい。
私は器が小さくて、傲慢で、それでいて体は素直で心は不器用だから、とても、彼程に器用には出来ないけれど。
それでも、彼を受け止められる器になりたい。
今の私は、彼の為なら、なんだってする。
出来ようが、出来まいが、関係ない。
だから、どうか、私を頼ってほしい。
今の私の幸せは、ぼくと彼が語り合い、微笑みながら日々を生きること、それだけだ。
私の人生は、ついに、ぼくだけのものではなくなった。
彼は、私の人生の片割れを、優しく受け止めて、背負ってくれた。
だから、私も、彼の人生の片割れを、優しく受け止めたい。
そして、背負ってゆきたい。
そのために、私は、強くなる。
そのために、私は、生きていく。